【事例7選】人事考課表の書き方を徹底解説 | 職種別のコメント例文を紹介BLOG
2023.9.25
自社の従業員を適切に評価するために人事考課表の存在は欠かせません。人事考課表は極めて重要なものですが、どのように作成すればよいのか、社員をどう評価すればよいのかで悩んでいる人もいるのではないでしょうか?
OKRやMBOを使った目標管理を行っている場合は、目標を達成するためのプロセスなども考課表を作成する際に重要な要素になります。
この記事では、人事考課表に盛り込みたい項目や具体的な書き方を職種別の例文と共に紹介します。部下・上司それぞれの観点から解説しますので、人事考課表の作成を難しく感じている人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1. 人事考課表とは?
2. 人事評価の重要性
3. 人事考課の3つの評価項目
4. 【7つの職種別】従業員と上司の人事考課書き方例文集
5. 従業員が人事考課表を書くときの3つのポイント
6. 上司が人事考課表を書くときの3つの注意点
7. 職種別の事例を参考に人事考課表の書き方を覚えよう!
人事考課表とは?
そもそも人事考課は従業員の査定のことです。普段の仕事ぶりを評価して、その結果が給与や賞与、役職などに反映されます。そして人事考課表とは、人事考課に使われる表のことです。
人事考課表は、半年もしくは1年に1回程度配布され、経営者や管理職などの上司だけでなく、部下である従業員本人も記述することが特徴です。なお、人事考課は人事評価と呼ばれることもあり、人事考課表も人事評価シートや自己評価シートなどと呼ばれることもあります。
人事評価の重要性
人事評価とは、社員の成果や能力を目標の達成度などに応じて評価することを指します。近年ではこれまで評価制度として、メインの手法であった「年功序列」から「成果主義」に切り替える企業も多くなってきています。そういった背景があり、社員の成果や能力を重視してそれに応じた給与や役職を決定する場合が増えてきました。
人事評価においては、各社員の成果を上司が公平に判断する必要性が高まったため、記載するコメントもより客観的な視点であることが重要です。
人事考課の3つの評価項目

人事考課表は社員ひとりひとりの成果を細かく評価し、給与や賞与に反映するために作成します。一般的に人事考課において指標とされているのは以下の3つです。
- 成果評価
- 能力評価
- 意欲評価
それぞれどのようなポイントに着目して人事考課表を作成すればよいのかを解説します。
成果評価
成果評価とは、あらかじめ定めた目標に対してどの程度の結果が出たかを評価するものです。一例として、「新規契約を20件獲得する」という目標を定めた場合を考えます。
締日時点で14件の新規契約を獲得した場合、社員の達成度は70%、22件なら110%です。評価する側は、はじめにこの結果を成果評価として人事考課表に盛り込みます。
評価すべき成果の内容を明記したら、成果につながったプロセスを分析して記しましょう。「目標を達成するために1日10件の営業活動を行い、平均1件の新規契約を獲得した」などと記すとわかりやすくなります。プロセスに関する分析を盛り込むときは、客観的に記すことが大切です。
能力評価
能力評価とは、各社員がもっている職務遂行能力を業務にどの程度発揮したかを評価したものです。主に以下のような能力に関する評価を盛り込みます。
- 企画力: 行うべき業務を遂行するための企画を立案する能力
- 実行力: 立案した企画を着実に遂行し、ゴールに到達する能力
- 改善力: 課題を解決するための方法を立案・実行する能力
- ヒューマンスキル: 他のメンバーとの人間関係を良好に保ち、連携して仕事を遂行する能力
- 業務知識: 業務に必要な知識を習得して活用する能力
- 理解力: 業務の目的や指示を正しく理解する能力
いずれも各個人の能力を適切に評価するために欠かせない指標ですが、主観的になりがちなポイントでもあります。そのため、業務成績がよい人に共通するポイントをベンチマークにするなど、客観的かつ公平に評価できる体制を整えることが重要です。
意欲評価
意欲評価とは、各社員の意欲や仕事に向き合う姿勢を評価するものです。ここには主に以下のようなものが含まれます。
- 勤務態度: 日々の勤務態度が良好か
- 責任感: やるべき仕事に対して責任をもって取り組んでいるか
- 誠実性: 勤勉に業務を遂行しているか
- 積極性: さまざまな課題に積極的に取り組んでいるか
- 協調性: 他者と協調して業務に取り組んでいるか
ただし、これらのポイントは評価する側の主観的な見方が強い要素です。そのため、意欲評価をあまり重視しすぎると不公平な評価になってしまう可能性がある点に注意してください。
【7つの職種別】従業員と上司の人事考課書き方例文集
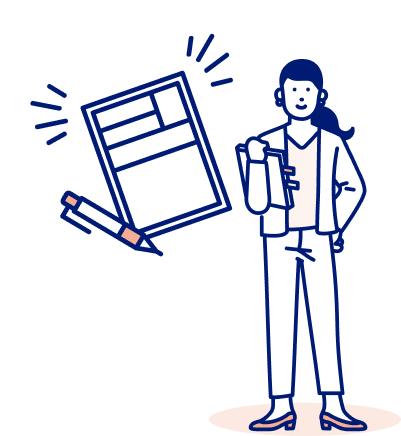
次に、職種別に人事考課の書き方を見ていきましょう。例文とともにポイントを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。今回紹介する職種は以下の7つです。
- 営業・販売職
- 企画・マーケティング職
- 事務職
- 技術職
- コンサルタント職
- 介護職
- 公務員
職種によって取り組むべき仕事の内容が異なるため、人事考課で意識すべきポイントにも違いがあります。
営業・販売職
営業・販売の場合、多くの企業において達成すべき目標が明らかになっているため、人事考課表も比較的書きやすいでしょう。人事考課表に盛り込みたい要素は以下のとおりです。
- 対象期間に挙げられた成果
- 成果につながったと考えられる要素
- 発見した課題
- 課題を解決するために今後できること
これらの要素をどのように盛り込めるのか、例文を見てチェックしていきましょう。
従業員の人事考課表の例文
| 今期は新規契約30件、リピート40件という目標に対してそれぞれ26件、34件という結果になった。いずれも達成率は85%である。目安となっている達成率70%を無事こえることができたが、これはリストの精査や優先順位の策定などにチームが一丸となって取り組んだ結果であると考える。 今後は新規商品のリリースも予定されているので、営業をさらに拡大する必要があると予想される。スムーズに営業を展開するためにも、マーケティングチームとの連携を強める必要があるだろう。 |
上司からの評価コメント例
| 当初定めた目標の85%という目安を上回る成果を挙げたことは評価できる。成約率を高めるために行った施策にも十分な効果があったと考える。 一方で新商品のリリースが控えていることを考えると、営業活動のさらなる効率化は優先的に解決すべき課題である。このままでは営業成績が徐々に低下する可能性が高いため、チームの枠を超えた連携は大きな課題となるであろう。 |
企画・マーケティング職
企画・マーケティング職は市場分析を行って新たなプロジェクトをスタートさせ、売上につなげるのが主な仕事です。人事考課表には自分が携わったプロジェクトに関して以下の情報を盛り込みましょう。
- プロジェクトの成果
- 成果につながるために実行したこと
- 実行するに至った根拠
それぞれのポイントを意識して作成した例文を紹介します。
従業員の人事考課表の例文
| 小売をメインターゲットとして開発した飲料についてアンケートを実施したところ、飲食店での取り扱いを希望する声が多数あった。そのため、飲食店での取り扱いを増やすための販促活動を企画・実行した。 その結果、製品を取り扱う飲食店がこれまでの3倍に増加した。現在進行中のプロジェクトに関しても、当初想定していたターゲット以外のニーズを探って効果的な販促を展開する必要があると考える |
上司からの評価コメント例
| メインターゲット以外に主要なターゲットを発掘してくれたことは評価に値する。とはいえ、収集したデータを細かく分析するとさらなる売上UPに繋がりそうな要素がいくつか見つかった。 これらのことを考えると、今後は細かいデータを分析して隠れた需要を掘り起こすことが必要になるといえるだろう。 |
事務職
事務職はルーティンワークが非常に多く、何をどのように評価すればよいのか迷うのではないでしょうか。仕事内容も変わらないことが多いので評価できないと思いがちです。
しかし、事務職とはいえ業務の精度を高めることは可能です。改善点を探して直すこともできるでしょう。人事考課表を作成するときには、これらの要素を盛り込むのがおすすめです。
従業員の人事考課表の例文
| 提出書類の不備が多く、差し戻しによる業務全体の遅延が発生していたのが今期の大きな課題だった。可能な限りヒューマンエラーによる不備を削減するために書類のテンプレートを用意するとともに、入力フォームにエラー検知機能を実装した。 その結果、1ヶ月あたり100件ほどあった書類不備による差し戻しが10件程度に減少したため、大きな効果があったといえる。 とはいえ、テンプレート化やエラー検知機能の実装が全ての書類に対して行われているわけではない。今後は扱っている書類全てにこの作業を行い、さらなる業務効率化を目指す必要があると考える。 |
上司からの評価コメント例
| 事務作業のミス防止は大きな課題であったが、それをテンプレート化によって大きく減少させられたのは高く評価できる。 今後はこの取り組みを全体に広げるとともに、ノウハウを共有する仕組みづくりにも取り組んでほしいと考えている。 |
技術職
技術職は企業の課題に対して工学分野からの解決を試みる職です。省エネや業務効率化など果たすべき役割は多岐にわたりますが、どのような成果が出たのか判断しにくい分野でもあります。
技術職の人事考課表を作成するときは、取り組みによってどのように業務を効率化できたか、どの程度のコストを削減できたかに着眼するといいでしょう。
従業員の人事考課表の例文
| 当社では数え間違いなどのヒューマンエラーによる在庫数のズレが恒常的に発生し、確認作業に多くの時間がかかっていて大変非効率だった。これを解決するために、IoT重量計を使った在庫管理システムを構築し、在庫管理の自動化を試みた。 その結果、在庫管理のほとんどを自動化でき、かかる時間を99%削減するとともにミスがほとんど発生しない環境が実現できた。その分コア業務に充てる時間を増やせ、全体の労働時間を30%削減することにもつながった。 |
上司からの評価コメント例
| 長年の課題であった在庫管理のトラブルをほぼ解決できたことは高い評価に値する。IoT重量計と管理システムの運用にかかる費用の負担は発生したが、それを上回るリターンを得られた。 今後は製造ラインの生産性向上にどのように取り組むかが考えるべき課題になると予想される。 |
コンサルタント職
コンサルタントはユーザーが抱える課題をヒアリングし、どのように解決すればよいのかを提案する職です。評価する際の視点は、顧客の課題を正しく把握して適切に対処できたか、途中で見つかった課題にどのように対処したかになるでしょう。
顧客との関係にどのような影響を及ぼしたかも盛り込むと、より説得力のある評価になります。
従業員の人事考課表の例文
| 小売業を営む既存顧客からシフト作成を効率化するICTツールの作成依頼を受けたため、希望シフトの収集からシフト作成、共有までを自動化するツールを提案した。 しかし、予算の都合で導入が厳しかったため、要望を再度ヒアリングして代替となるツールを提案して受注に至った。 |
上司からの評価コメント例
| モデルプランに固執することなく、顧客の要望や予算の都合をきちんと把握して代替案を提示し、受注につなげたことは評価に値する。 今後は、販売目標をどのように達成するかにも注目すればさらなる売上向上に繋げられると考える。 |
介護職
介護職は要介護者に対する生活介助や身体介護が仕事なので、ルーティンワークが多いのが特徴です。業務そのものが目に見える成果として現れる職種ではないため、スキル向上や安全確保、環境整備に対する取り組みを盛り込むのがよいでしょう。
なんらかの目標を掲げているなら、達成度合いを測る指標を用意して評価基準にするのもひとつの方法です。
従業員の人事考課表の例文
| 当施設では利用者の安全確保が最優先であり、施錠忘れによる徘徊を予防するのが最大の課題だった。ヒューマンエラーをゼロにするのは非常に難しいため、フロアごとの施錠をオートロック化することで施錠忘れを解消できた。 |
上司からの評価コメント例
| 利用者の安全を確保するための施策を率先して考え、事故の予防に取り組んでいることは評価に値する。引き続き課題解決に取り組むとともに、今後はスキルやノウハウの共有にも意識を向けてもらいたい |
公務員
公務員は国(中央省庁・行政府・立法府)や地方自治体(都道府県・区市町村)の職員です。公務員の職務は明確な目標や果たすべき仕事が存在しないケースも多く、評価するのが難しいと感じてしまうかもしれません。
そのような職種の場合は、業務効率UPのための取り組みや作業フロー改善の取り組みなどを盛り込むとよいでしょう。
従業員の人事考課表の例文
| 関連法令の改正に伴い、変更された申請書の様式に目を通し、承認作業が円滑に進むように業務フローを改善した。具体的には、変更点をリストアップして新たに行わなければならなくなった作業とそうでない作業を明記し、新たな業務フローに慣れるまで確実にチェックした。 その結果、チェック不備による承認作業の遅延を予防でき、業務をスムーズに進められるようになった。 |
上司からの評価コメント例
| 法令改正や申請書様式の変更はミスを誘発するものであり、これにうまく対応できて業務効率を低下させなかったのは評価に値する。今後も同等の業務は定期的に発生すると見込まれるので、ノウハウを共有する仕組みづくりが必要だと感じている。 |
従業員が人事考課表を書くときの3つのポイント
人事考課表にはコメントを書く欄が設けられています。従業員が自身で書く際は、工夫が必要です。
- 前向きな表現で書くこと
- 客観的に記すこと
- 簡潔な表現を用いること
を意識することが大切です。以下で詳しく説明します。
前向きな表現を使う
人事考課表は、従業員本人が経営者や役職者といった上司にアピールできる絶好の機会です。なるべく前向きな表現で書くことを心がけましょう。
もし失敗をしてしまった場合、反省することは大事ですが、反省から得られたことを前向きな表現で書くことが肝心です。失敗をくり返さないために、次に活かすための改善策を必ず記載しましょう。
客観的なデータを元にする
正確で客観的なものごとを記すことも重要です。実情よりよく書きすぎることはもちろんNGですが、ひかえめに書きすぎることも望ましくありません。
もし具体的な数値で決められた目標があれば、達成度を数値で示し、結果に対する分析と実際に行った取り組みを書いて適切にアピールしましょう。会社はチームプレーですので、チームに貢献したことも書き添えると印象がよく、おすすめです。

人事部は華々しい成果を出す人だけでなく、自分の仕事を客観的に見て今後に活かせる人材を高く評価する傾向があります。正確に自己を見つめ、客観的な評価を記載しましょう。
簡潔な表現を用いる
上司は忙しい業務の合間に人事考課表を確認します。読む気にならないように感じるような長い文章は避けたほうがよいです。
「だ・である調(常体)」を用いて、シンプルで簡潔な文章を作りましょう。なるべく数値化すると、簡潔かつ客観的で説得力のある文章になりやすいです。
上司が読むことを考えて、推敲してから提出することをおすすめします。
上司が人事考課表を書くときの3つの注意点
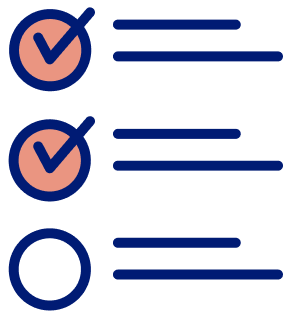
続いて、上司が人事考課表を作成するときの注意点を見ていきましょう。上司は以下の3つのポイントを意識して作成するとよりよい内容のものができあがります。
- なるべく具体的な内容を書く
- 良い点・悪い点の両面を書く
- 他の社員と比較しないように書く
なるべく具体的な内容を書く
上司が作成する人事考課表は、客観的な視点を保ちつつ以下の内容を盛り込みましょう。
- 期間中に達成した成果
- 対象社員が日々の業務で積み重ねてきた努力・行動
- 成果を達成するのに役立った能力
これらの情報を正しく盛り込むためには、日頃からよく部下を観察して成果に目を留めることが大切です。さらに、これまでの成果を振り返りつつ、将来に繋げられる内容を盛り込めるとなおよくなります。
部下本人が気づいていない改善点があれば適切にフィードバックし、より高い成果を出せるようにマネジメントしましょう。
良い点・悪い点の両面を書く
成果を通して明らかになったポイントは、良い面と悪い面の両方を記載することが大切です。プラス評価になる部分を記載することで対象者のモチベーションを高い状態に保ちつつ、マイナス評価になる部分を指摘して改善点を教えましょう。
良い面・悪い面の両方を取り上げることで、社員のさらなる成長を促せます。プラス評価になっている部分はより伸ばす方法を、マイナス評価になっている部分は改善方法を盛り込むとより効果的です。
他の社員と比較しないように書く
人事考課表を作成するときに他の社員と比較すると、モチベーションを下げてしまう原因になりかねません。人事考課表を作成する主な目的は社員のモチベーションを高く保ち、業績を伸ばすことです。
このことを常に意識し、言葉を選んで効果的な文章を記すようにしましょう。人格否定や事実の歪曲、不適切な表現も避ける必要があります。
職種別の事例を参考に人事考課表の書き方を覚えよう!

人事考課表は社員の成果を評価して報酬に反映するための資料であると同時に、モチベーションを維持して全体の業績UPにつなげるための資料でもあります。しかし、場合によってはどのように作成すればよいのか迷ってしまいがちです。
職種によっても記すべき内容は異なります。人事考課表の書き方で迷っている人は、この記事で紹介した職種別の事例を参考にしつつ自社にマッチしたものを考えてみてください。
もし、社員ひとりひとりの結果が明らかになっておらず、作成が難しいと感じるなら目標管理の方法を見直す必要があるかもしれません。以下の記事では成果につながる目標管理の方法についても紹介していますので、ぜひあわせてご参考ください。
本記事を執筆したResilyはスタートアップから大企業まで幅広い組織で採用され始めている「OKR」を管理するツールを提供しています。
- OKRを知らない方
- 聞いたことはあるけど詳しくは知らない方
- OKRをこの機会に勉強してみたい方
は、ぜひこちらの記事もご覧ください。59ページのOKR教科書という資料も記事内で無料で公開しています。登録なしでODFダウンロードすることもできますので、ぜひご活用ください。
おすすめ記事
