ジェンダーギャップ指数とは?意味、問題と対策を紹介BLOG
2021.6.21
男女雇用機会均等法の制定以降、男女格差を無くそうと日本でもさまざまな取り組みが行われています。そこで重要になるキーワードが「ジェンダー・ギャップ」です。仕事以外の部分でも男女の平等を図っていく必要があります。また、ジェンダー平等は国連の持続可能な開発目標(SDGs)の一つにも設定されており、世界中でどのように進めていくのか議論が行われているところです。しかし、日本は各国と比べてジェンダー平等に関して、かなり遅れを取っているという現状があります。
そこで今回は、ジェンダー平等の達成度を示す「ジェンダーギャップ指数」を基に、世界各国との比較や日本の課題について詳しくみていきます。
ジェンダーギャップ指数とは?

そもそも「ジェンダーギャップ指数」とはどのようなものなのでしょうか。
ジェンダーギャップ指数とは、各国の男女間格差の状態を14個の項目で測ったものを指します。14個の項目はそれぞれ重み付けがされており、値が1に近づくほど男女平等が進んでおり、0に近づくほど男女格差が大きくなっていると判断されるものです。14の項目は「経済参加」「教育」「健康」「政治参加」という4つのジャンルに分けることができ、それぞれに細かい指標が設定されています。ジャンルごとにスコア化され、その総合スコアを基に世界各国のランキングが作成されているのです。
日本のジェンダーギャップ指数の現状
世界経済フォーラムが発表している各国のジェンダー・ギャップ指数の状況を発表した2020年版のレポートによると、日本は121位という結果でした。これは計測している国の中でも下位に位置しており、G7では最下位で先進国で最も男女格差が大きいということになります。
各分野別のスコアを見てみると「経済」は0.598で115位、「教育」は0.983で91位、「健康」は0.979で40位、「政治」は0.049で144位という結果で、「健康」以外の項目は軒並み世界的に遅れを取っていることが分かります。特に政治参加の項目が進んでいないのが特徴的で、日本の伝統的な社会構造や風習、政治関心度の低さが課題として挙げられるでしょう。このような日本の課題に関しては、後の項目で詳しく解説していきます。
世界のジェンダーギャップ指数との比較
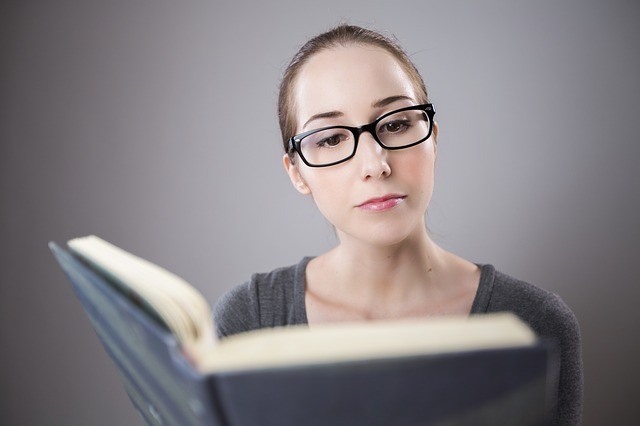
では、世界各国のジェンダーギャップの現状はどのようになっているのでしょうか。
日本と世界各国の状況を比較してみることで、課題やこれからの対策を考えていきましょう。
ジェンダーギャップにおける世界共通の課題
ジェンダー・ギャップにおける日本の状況として特徴的だったのが、「政治」での0.049というスコアでした。ただ、この「政治」分野におけるジェンダー格差の問題は、日本だけのものではありません。世界の平均値においても「政治」は0.218と「教育」の0.950、「健康」の0.975と比べて低くなっています。また、「経済」においても、日本の現状と同様0.583と低くなっているのです。つまり、「政治」及び「経済」分野におけるジェンダー格差は日本だけの課題ではなく、世界的な課題だと言えるでしょう。とはいえ、世界的な平均と比較しても、日本のスコアはかなり低いのでより重点的に対策をしなければならないとも言えます。
G7参加国との比較
日本も参加している世界的な大国が集まるG7の中では、どのようなジェンダーギャップ指数の傾向があるのでしょうか。
前述した通り、このG7参加国の中で日本はジェンダーギャップ指数のスコアが最下位という結果になっています。さらに日本の121位という結果に対して、他の参加国の結果はドイツ11位、フランス15位、カナダ19位、イギリス21位、アメリカ53位、イタリア76位となっており、日本のジェンダー格差が抜きん出て遅れを取っていることが現れているのです。
各評価項目に関してみてみると、このG7各国と比べて日本は読み書き能力や中等教育の分野においてはジェンダー格差が見られないという評価であり、ランクの世界トップクラスです。ただ、国会議員数や政治家・経営管理職数ではどれも100位以下になっており、政治や経済を担うリーダーの中でジェンダー平等が実現できていないことが課題だと言えます。
ジェンダーギャップの問題点

そもそもジェンダーギャップが大きくなることで、どのような問題点があるのでしょうか。改めて確認しておくことで、これからのジェンダーギャップへの対策を考えていくことができるはずです。
ここからはジェンダーギャップの問題点をいくつか紹介していきます。
優秀な人材の損失
男女の特性の違いはありながらも、仕事における能力は基本的には差がないはずです。にもかかわらず、昔から根付いている価値観や慣習、子育てと仕事の両立ができないからやむなく断念してしまうことことから女性の社会進出が進まないことで、潜在的な優秀な人材を雇用できない可能性が高まります。ジェンダーギャップがなくなることで、等しく優秀な人材と出会う可能性を広げることができ、企業のより一層の発展につなげることができるでしょう。
女性の意見が反映されない法整備が進む
女性が政治に参加する機会が少なくなることで、国や自治体の重要な意思決定の場面で女性の意見が反映されず、結果的にさらにジェンダーギャップが広がるような不十分な法整備に繋がってしまいます。ジェンダーギャップがなくなることで、男女それぞれの観点からバランスの取れた意思決定を行うことができるようになり、個人が性別の違いに関係なく自身の個性を発揮して仕事に取り組んだり、生活を営んだりできるようになるでしょう。
女性への暴力の助長
ジェンダーギャップが引き起こす課題は、社会的なことだけでなく暴力や虐待など直接的な危害が及ぶことも挙げれられるでしょう。また、直接的な暴力だけでなく、言葉による差別発言やセクハラ・モラハラなどもジェンダーギャップが大きくなることによって助長されていきます。
日本のジェンダーギャップへの対策

ここまでは日本の現在のジェンダーギャップに関する世界的な立ち位置を確認してきました。かなり課題が山積みであるということは明確ですが、現在の状況に至るまでに日本はどのようなジェンダーギャップに関して対策を行ってきたのでしょうか。
ここからはこれまでの日本のジェンダーギャップに関するさまざまな対策に関して詳しく紹介していきます。
女性活躍推進法
女性活躍推進法とは、2016年に安倍内閣が施行したもので、女性が働きやすい環境づくりをするよう企業に求める法律のことです。「採用や昇進についての平等」「仕事と家庭が両立できる環境づくり」「「仕事と家庭の両立について意思決定できる」という3つの基本原則があり、ジェンダーギャップ指数の低さが喫緊の課題であることから短期集中で取り組みを進めるために10年間の期限が定められています。
この法律の制定の背景としては、日本の職場におけるジェンダーギャップの大きさが挙げられます。よって、基本原則を遵守することで、女性が自身の意志でキャリアを歩むことができ、自分のスキルや強みを発揮して仕事ができる社会を目指すことが期待できます。
育MEN(イクメン)プロジェクト
育MEN(イクメン)プロジェクトとは、厚生労働省が推進しているもので育児を行う男性を支援することを目的にしています。「子育ては女性がするのものだ」という考えが日本では強く根付いていることがジェンダーギャップを大きくしていることから、男女が両方共仕事と育児を両立できるよう支援する取り組みになっています。具体的には男性が育児休暇を取りやすくなるよう企業や地域に対して意識啓発を行ったり、社会的な機運を高めるための周知啓発の活動を実施したりするものです。このプロジェクトが進んでいくことで、女性だけ育児や家事の負担が大きくなりすぎず、社会で活躍したいという女性が増えることが期待できます。このプロジェクトは平成22年に発足しましたが、翌年の平成23年度では男性育児休業取得率が過去最高となりました。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律とは、政治分野での男女格差を是正することを目的に平成30年に公布・施行されたもので、具体的には男女の候補者数ができるだけ均等になることを目指すことなどを基本原則としています。国や地方公共団体それぞれに男女候補者数の目標を設定し、自主的にジェンダーギャップに対する取り組みを促しています。この法律の制定によって、女性が議会へ参画しやすい社会になることで性別による社会的な偏見をなくすことができ、男女それぞれが特性や個性を生かしながら暮らしていくことができるのです。
ジェンダーギャップに関する日本の課題とこれから
これまで述べてきた通り、ジェンダーギャップの解消は世界的な課題ではありながらも、特に日本においては喫緊の課題であることは明確です。ジェンダーギャップは昔からあるものですが、国連が持続可能な開発目標にて「ジェンダー平等」を掲げていることからも、これからは従来やってきた取り組みに加えてさらに積極的に環境や制度の整備を実施していかなければならないでしょう。
日本においては、政治分野及び経済分野での女性リーダーの輩出が大きなポイントになることでしょう。どちらの分野においても中核を担う女性が増えていくことで、女性ならではの視点が社会的に反映されるようになり、さらにジェンダー格差を小さくしていくことができます。そのためには「男性が働き、女性は育児や家事をする」など従来の価値観や偏見をなくし、それぞれが個性を発揮し合ってよりよい社会を目指していけるように環境を整えていく必要があります。
おすすめ記事
