リフレーミングとは?意味、種類、メリットを紹介BLOG
2021.6.30
「リフレーミング」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
心理学の分野でよく使われますが、近年では仕事をうまく進めるために身につけたい視点としてリフレーミングが注目を集めています。ただ、「聞いたことはあるけどよく分からない」「うまくリフレーミングを身につけられない」という方も多いはずです。そこで今回はリフレーミングに関して、種類や具体的なメリットや活用例から活用のポイントまで詳しく紹介していきます。身につけておくと生活のさまざまな場面で役に立つ視点であるため、是非こちらの記事を参考にリフレーミングを実践してみてください。
リフレーミングとは?

リフレーミングとは、物事を見る枠組みを変えて別の視点で見直すことを指します。例えば、食べ物が半分余っている時に「あと半分しか残っていない…」という捉え方もあれば、一方で「まだ半分も残っている」と捉えることもできるでしょう。このようになにごとでも同じ事象に対して状況や考え方によって別の捉え方が可能です。その捉え方を自ら意識的に変化させることをリフレーミングと呼びます。
このような捉え方を身につけることで、ネガティブな状況でもいい効果をもたらしてくれるでしょう。
リフレーミングの種類
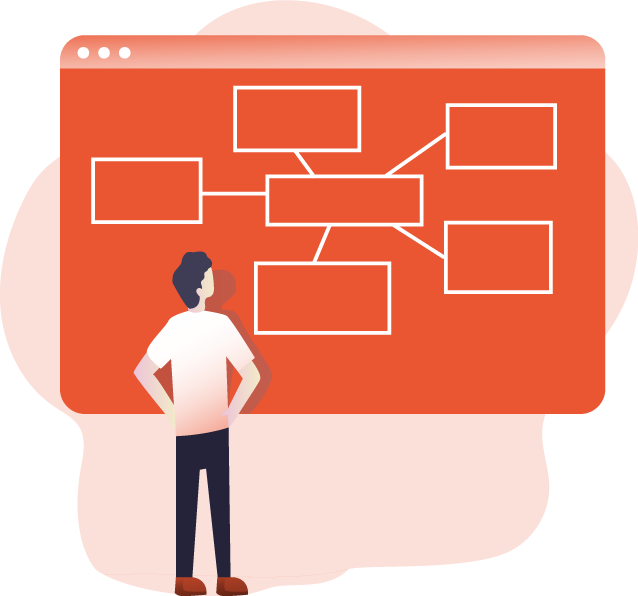
リフレーミングには「置かれている状況のリフレーミング」と「内面に関する内容のリフレーミング」の2種類があります。同じリフレーミングでもそれぞれ特徴があるため、どのようなものなのか、ポイントを抑えておきましょう。
置かれている状況のリフレーミング
置かれている状況のリフレーミングとは、人や出来事が置かれている状況の枠組みを考え直すことを指します。例えば怪我をしてしまって日常生活に支障をきたしてしまった際は、「怪我のせいで仕事は進まなかったが、自分の時間を確保することができた」と捉え直したり、一緒に仕事をするメンバーに関して「考えすぎてしまって行動するのが遅いが、思慮深い分物事の本質を捉えることができる」と他人の良い点を見つけることもできるでしょう。
内面に関する内容のリフレーミング
性格や悩み、価値観など内面に関する個々人の感じ方の枠組みを見直すことを内面に関する内容のリフレーミングと呼びます。例えば、神経質で細かいことばかり気にしてしまう性格に関して「神経質だが、細かなことにも気を配れる」とポジティブに捉え直したり、経験がないことをする際に「全く経験はないが、新しいことに挑戦できる良い機会だ」と捉え直すことです。
リフレーミングのメリット

物事の視点を変えて捉え直すリフレーミングには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。リフレーミングのメリットはさまざまですが、ここでは「モチベーションの向上」「チャレンジ精神が身に付く」「人間関係が良好になる」という3つのメリットについて、それぞれ詳しく紹介していきます。
モチベーションの向上
仕事をする際にモチベーションが上がらず、なかなか成果を出すことができないという方も多いでしょう。そんな時でもリフレーミングを身につけることで、モチベーションの向上につなげることができます。
例えば、大勢の前でプレゼンテーションをする機会があった際に、通常では「人前で話すのは緊張するし、失敗するのでは…」と不安に感じてしまうこともあるでしょう。そこでリフレーミングを使って捉え方を変えてみると、「多くの人が自分の話を聞いてくれている」「他の人に少しでも役に立てるように真剣に話そう」とポジティブになることができ、プレゼンテーションにモチベーション高くのぞむことができるはずです。
チャレンジ精神が身に付く
リフレーミングを身につけることで、苦手意識を克服して色々なことにチャレンジできるようになるでしょう。リフレーミングによって苦手なことに関して「苦手だからやめておこう」「このまま苦手なままでいいや」という捉え方から、「できることを増やす機会になる」「これが出来れば自信を持てる」というポジティブな捉え方に変えることができます。チャレンジ精神が身に付くことで、前述したモチベーション向上と合わせて自分ができることの幅を広げて成長していくことができるでしょう。
人間関係が良好になる
自分にはない考えや価値観を持った人と関わる際に、なかなかうまく人間関係を構築できないという人は多いはずです。リフレーミングを身につけることで、自分と異なった考えを持っている人の発言や行動に対しても、「考え方が理解できずに戸惑う」「自分とは違うから受け入れられない」とネガティブな捉え方ではなく、「自分にはない観点を持っている」「知らない世界を教えてくれる」という風にアドバイスや新しいアイデアのきっかけとして捉えることができるようになるでしょう。
リフレーミングを実践する具体的な手法
では実際にはどのようにリフレーミングを実践したら良いのでしょうか。リフレーミングにはさまざまな種類がありますが、今回は5つの手法をそれぞれ詳しく紹介していきます。
言葉のリフレーミング
言葉のリフレーミングとは、落ち込んでいる時やうまくいっていない時に出てくるネガティブな発言の捉え方を変えて、モチベーションを取り戻す手法のことを言います。どんなネガティブな言葉でも、捉え方によってポジティブな側面を持っているものです。例えば「消極的」という言葉は「自分の意見を表明できない」「チャレンジしない」という欠点として捉えられてしまいがちですが、裏を返すと「周りを尊重できる」「リスクを慎重に検討できる」と捉えることもできるでしょう。
As IFのリフレーミング
As IFのリフレーミングとは考えが行き詰まってしまった際に「もし○○だったら…」と捉え直すことで、新しい観点での気づきを得られるリフレーミングの手法です。進んでいないことや思い悩んでいることに対して「もし先輩の○○さんだったらどのようにするか」「もし○○だった場合、どうするべきか」と問いかけることで、これまで気づかなかった課題に気づいたり、新しい発想につなげることができます。このリフレーミングを繰り返すことで、何事に対しても多角的な視点で捉えることができるはずです。
時間軸のリフレーミング
時間軸のリフレーミングとは、今起きている事象に対して時間軸をずらして捉える手法のことです。例えば、仕事で失敗をしてしまった時に「未来の自分はこの失敗をどう考えるだろうか」「過去の自分は同じ失敗をしただろうか」など、未来や過去の自分はどう捉えるかを考えます。この時間軸のリフレーミングを身につけることで、何か失敗やネガティブなことが起こってしまった場合でも、落ち込んでしまうことなく未来のための行動を見出すことができるでしょう。
解体のリフレーミング
解体のリフレーミングとは、フレームそのものを解体して捉え方を変える手法のことです。例えば「仕事で思った成果が出ない」と悩んでいるのであれば「どんな状況だと成果が出ないのか」「どの程度の成果が出れば良いのか」「誰と比べて成果が出ないのか」など、5W1Hで枠組みを解体していきます。こうすることで漠然とした悩みや不安具体的な課題になり、改善策が思いついたり、そもそも思い過ごしだったことに気づくことができるのです。そのような捉え方で仕事をすることで、健全なメンタル状態で仕事を進めることができるでしょう。
wantのリフレーミング
wantのリフレーミングとは、何か行き詰まっている状況に対して「代わりにどうしたいか」を問いかける手法です。例えば、上司に仕事上のミスで怒られてしまった際に「どうすればよかったんだろうか…」と思い悩んでいる場合、「では、どうされたかったのか?」を自身に問いかけます。そうすることで「評価されたい」や「怒り方を工夫してほしい」など自身の欲求を引き出すことができるため、そのために何をすれば良いか未来に向けたアクションにつなげることができるのです。
リフレーミング活用のポイント

リフレーミングはただやり方が分かっているだけでは、メリットを最大限活かすことはできません。活用するためのポイントを抑えて、具体的な手法を実践することが重要です。
ここからはリフレーミングを活用する上で抑えておきたいポイントをいくつか紹介していきます。
トレーニングの習慣をつける
リフレーミングは具体的な手法を何度も繰り返して身につける「技術」です。技術を磨き上げるためにはトレーニングして経験を積み重ねていくことが必要になります。そのため日常生活で起きる事象や他人の言動に対して「別の表現で言い換えることができるか」「捉え方を変えてプラスに変えることができるか」を出来るだけ考えるようにし、リフレーミングの精度を高めていきましょう。
他人へ共感する
他人へのリフレーミングを実践する場合は、相手の立場に立った上で「相手が自分に伝えたいのは何なのか」「それを受けての自分の発言はどんな影響を与えるか」など、相手への共感をベースにすることが重要です。相手の言動の意図を考えず、ただポジティブな言葉をかけるだけでは、最悪の場合自分の価値を下げることに繫がるので注意しましょう。
リフレーミングのポイントを抑えて実践しよう

起こった事象や他人の言動は、どんな枠組みに当てはめて受け止めるかによって与える影響が全く異なります。ネガティブになってしまう時や行き詰まっている時、人間関係がうまくいかない時は、今回紹介したリフレーミングの手法や活用のポイントを抑えて実践することで、解決の糸口を見つけられる可能性が高いです。
いつでもリフレーミングを実践できるように、日頃から意識的に実践していきましょう。
おすすめ記事
