DESC法とは?意味、手順、メリットとデメリットを紹介BLOG
2023.6.27
⇒OKR導入から実践までのパーフェクトガイド「OKRの教科書」を無料で公開中
DESC法とは、自分の要望を4つの段階に分けて、相手とポジティブなコミュニケーションを取る手法です。
「誰かにお願いをするのが苦手だ…」
「相手を説得したいけどなかなかうまくいかない…」
仕事上でコミュニケーションを取る際に、このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
誠実なコミュニケーションを取るためには、自分の意見をただ一方的に伝えるだけではなく、相手の感情にも配慮することが重要になります。そのために活用されるのが「DESC法」というコミュニケーション手法です。DESC法という用語は聞いたことがあるが、「意味がよく分かっていない」「どう活用すればいいか分からない」という方もいるはずなので、今回はDESC法についてメリット・デメリットや活用のポイントまで詳しく解説していきます。
DESC法とは?

DESC法とは、相手の感情に流されずに自分の意見や思っていることを相手に伝えるコミュニケーションの技術のことを指します。「私はこうしたい」と自分の主張ばかりしていては、相手との関係性や事態を悪化させてしまう可能性が高いです。DESC法を使って譲歩しながらも前向きなコミュニケーションにすることで、自分と相手の双方にとってスムーズに物事を進めていくことが可能になります。
基本的にコミュニケーションは、自分の主張を押し通す「アグレッシブ型」、相手の主張を優先させる「ノンアグレッシブ型」、相手のことも尊重しながら自分の意見を率直に伝える「アサーティブ型」に分類することができます。DESC法は「アサーティブ型」のコミュニケーションになり、主張が違う相手とも折衷案を見つけやすくなるのが特徴です。
DESC法の手順

具体的にDESC法はどのように実践するのでしょうか。DESC法は「Describe:描写する」「Explain:説明する」「Specify:提案する」「Choose:選択する」という4つの単語の頭文字を取ったもので、この手順に沿ってコミュニケーションを取ります。
ここからはそれぞれのステップについて詳しく解説していきます。
Describe(描写する)
「Describe(描写する)」では、顕在している問題や相手の言動に関して客観的に描写します。ここでのポイントは、あくまで客観的に事実を述べることで、自分の感情を入れたり「〜かもしれない」という憶測を伝えたりしないように注意しましょう。例えば、何かを依頼されたが断りたいときに「忙しいので無理です。」と感情的になるのではなく、「15時までに○○を終わらせなければならないため、それに時間を使えません。15時以降でもよければ引き受けられます。」と伝えましょう。
Explain(説明する)
「Explain(説明する)」では、描写した客観的な事実に対して自分の意見や感じていることを相手に伝えます。自分が思っていることを伝えるステップですが、感情に任せて攻撃的になっては本末転倒なので、あくまで理性的に表現するのが重要です。上司からの依頼に当てはめると「余裕があれば引き受けたいとは思っているのですが、こういった状況のためご理解いただけると助かります。」のように、相手の気持ちも受け止めながら率直に自分の思いを伝えましょう。
Specify(提案する)
「Specify(提案する)」は、状況を変えられるような代替案や自分がしてほしい内容を相手に伝えるステップです。同じ頭文字から始まる「Suggest」を当てはめる場合もあります。提案する際には相手に何かを強制させたり、現実的ではない提案にならないように配慮しましょう。依頼に対しては「本日中の対応は難しいため、明日優先的に対応するのはいかがでしょうか?」と、現実的かつ相手に検討の余地を与えるような提案をします。
Choose(選択する)
「Choose(選択する)」では、相手が提案を受け入れるかどうかによって選択肢を提示します。提案した内容が必ずしも相手に受け入れられるわけではないため、断られた場合に関してもしっかり想定しておくのが重要です。そうでなければ、こちらの一方的な押し付けになってしまい、相手に不快な思いをさせてしまう可能性があります。例えば、「明日対応する」という提案が断られた場合は、「他に対応できる人を探す」「現在の業務より依頼事項を優先できるか確認する」といった選択肢が考えられるでしょう。
DESC法のメリット・デメリット

DESC法を活用してコミュニケーションを取ることで、さまざまなメリットを得ることができます。ただ一方で、デメリットがあることも理解しておきましょう。ここではDESC法のメリット・デメリットの双方を確認していきます。
DESC法のメリット
DESC法のメリットとしては、相手に納得してもらいながら自分の意見を伝えることができることが挙げられます。アグレッシブ型のコミュニケーションでも自分の意見を伝えることはできますが、相手の納得感に配慮できていないため、仕事を進めていくことは難しいでしょう。DESC法で相手の感情にまで配慮したコミュニケーションを取ることで、信頼関係を築きながら物事を合理的に進めていくことが可能になります。
DESC法のデメリット
一方でDESC法にも少なからずデメリットが存在します。ひとつは「自分の意見を強く通せない」ことです。どうしても主張しなければならない意見や、明らかに相手が社会的に間違っている場合はDESC法でのコミュニケーションは向いてないかもしれません。また、相手の反応に応じて「複数の選択肢を用意する必要がある」ことも、デメリットになり得るでしょう。コミュニケーションを取る度にいくつも選択肢を考えて相手に投げかけるのは、負担が大きくなってしまう場合もあります。
DESC法の活用例
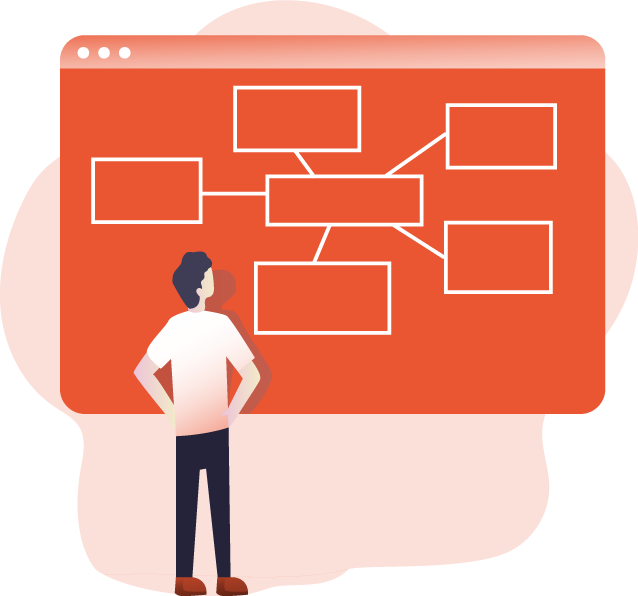
DESC法はさまざまなコミュニケーションの場面で活用できます。
ここからはDESC法が活用できる具体的な場面例を紹介していくので、自身の環境に合わせて使い方をイメージしてみてください。
価格交渉
ビジネスシーンでよくあるのがクライアントとの価格交渉です。価格交渉において双方が納得のいくコミュニケーションが取れないと、今後の取引に支障が出てしまうでしょう。そのためDESC法が有効な手段になります。
具体的な会話の手順は以下の通りです。
・Describe(描写する)
「ご希望の金額での取引を社内検討させて頂きましたが、取り決めで値引きが難しい状況です。申し訳ございませんが、○○円での取引にてお願いいたします。」
・Express(説明する)
「ご期待には沿えませんが、貴社とは今後ともお付き合いさせて頂きたく存じます。」
・Suggest(提案する)
「値引きは難しい状況ですが、今後優先的に商品のご案内をさせて頂けるよう調整させて頂きますがいかがでしょうか。」
・Choose(選択する)
提案を受け入れられる場合:「今後オプションの特別価格も貴社に優先的にご案内させて頂きます。」
提案を受け入れられない場合:「改めて上司に確認させて頂きます。」
意見が異なるメンバーの同意を得る
チーム内でのミーティングにおいて、自分の意見に対して別の意見を持っているメンバーから同意を得たい場合もDESC法を活用できます。例えば、何か新しいシステムを導入を検討している場面で反対をされた場合は、以下のような手順になります。
・Describe(描写する)
「現在自社には〜〜という課題があり、そのような課題を解決する○○というシステムがあります。」
・Express(説明する)
「□□さんが費用対効果に関する懸念を持っていることは承知しました。ただ、〜〜という課題は早々に解決しなければ大きな損失に繋がりかねません。」
・Suggest(提案する)
「初めから大きな投資をするのはリスクが大きいということであれば、少数のチームからシステムの導入を試験的に実施し、テストするのはいかがでしょうか。」
・Choose(選択する)
提案を受け入れられる場合:「導入に関しては責任を持って取り仕切ります。」
提案を受け入れられない場合:「他社のシステムについても調査し、導入コストについて再検討します。」
DESC法活用のポイント

ここまで解説してきた通り、さまざまなコミュニケーションの場面でDESC法は活用することができます。手順に沿ってコミュニケーションをすることである程度効果はありますが、有効に活用するためにはポイントを抑えておくことが重要です。
最後にDESC法活用のポイントをいくつか紹介していきます。
「Choose(選択)から考える」
DESC法を使ってコミュニケーションを取る際は、最後のステップである「Choose(選択)」から逆算して組み立てるようにしましょう。つまり、結論に向かってそこに行き着くための構成を作っていくイメージです。結論が明確になっている上でDESCの手順に沿うことで、より相手に納得感を持たせることができます。
強制しない
DESC法はそもそも双方の納得を目指したコミュニケーションであるため、相手に強制的に選択肢を押し付けたりしてはなりません。ある程度自分が想定した結論にもっていくために工夫はしますが、相手が拒否することも容認する必要があります。そうすることで、信頼関係を築きながらさまざまな世代・立場の人と対等にコミュニケーションを取ることができるでしょう。
DESC法を活用してコミュニケーション能力を高めよう
DESC法で最も重要なのは、相手を思いやる気持ちを持ってコミュニケーションをとることです。そのためには、日頃からDESC法を意識したコミュニケーションを取る回数を増やしていくのが良いでしょう。DESC法でのコミュニケーションが習慣付けば、仕事でもプライベートでも良好な人間関係を築いていけるはずです。
OKRの運用では、毎週初めにチェックインミーティングを実施しますので、無理なくDESK法を実践することが可能です。また、Resilyでは進捗情報や更新時のメモなどもデータが蓄積・可視化されますので、データドリブンでメンバー間の会話ができるようになります。
今回解説したポイントを抑えながら、DESC法を実践してみてください。
おすすめ記事
