インテグリティとは?注目される背景、メリット、事例を解説BLOG
2021.10.4
組織のリーダーやマネジメントを担う立場の人に求められる重要な資質の一つとして、「インテグリティ(Integrity)」という概念が注目されています。組織を円滑に機能させるためにも、インテグリティの基本概念を理解しておく必要がありますし、これからの時代に特に重要視されていく概念なのは間違いありません。
なぜ今、インテグリティが重要な資質として挙げられるようになってきているのでしょうか。今回は、そんな「インテグリティ」の意味から、取り組み事例まで詳しく解説していきます。
- インテグリティとは?
- インテグリティが注目される背景
- コンプライアンスとの違い
- インテグリティ浸透のメリット
- インテグリティを持つ人の特徴
- インテグリティ対策の事例
インテグリティとは?
「インテグリティ(integrity)」とは、もともと「誠実」「真摯」「高潔」などの概念を意味する言葉です。インテグリティは、組織を率いるリーダーや管理職などのマネジメント職に求められる最も重要な資質として、1950年代にピーター・ドラッカーによって主張されました。次第に、企業経営や組織マネジメントの領域でも使われる用語となりました。現在では、欧米を中心に、経営理念や企業倫理に関わるビジネス用語として定着しています。
インテグリティの重要性を説いたピーター・ドラッカーは、「インテグリティこそが組織のリーダーやマネジメントを担う人材にとって決定的に重要な資質である」と述べています。ただ、インテグリティの定義については、ドラッカー自身が「難しい」と答えており、インテグリティが欠如している人物を明示することで、逆説的にインテグリティの定義を浮かび上がらせようとしています。
インテグリティについて考える例の一つとして、人事採用について考えてみてください。採用の際は、どうしてもその人の学歴や資格、能力といったものに目を向けがちですが、倫理観の欠けた人物を雇用することは、企業にとって思わぬリスクを招く恐れがあります。
いくら社内規則などを強化しても、実際に従業員一人一人の行動を管理するのは不可能でしょう。最終的には、従業員の一人一人の心持ちに頼らざるを得ないのです。そのため、人事部門においては、雇用の段階でインテグリティを意識した活動を行っていくことが重要と言えるでしょう。
インテグリティが注目される背景
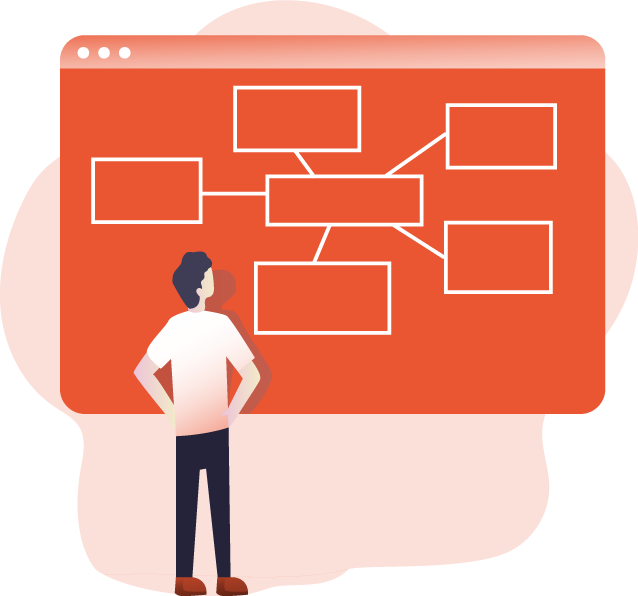
インテグリティがここまで注目されるようになった主な理由は3つあります。
行き過ぎた成果主義
1つ目は、行き過ぎた成果主義による反省です。行き過ぎた成果主義により、何が何でも成果を出さなければならないと無理した企業活動を行った結果、多くの不祥事が起こってしまいました。その後、コンプライアンスを重視した法令遵守を徹底することもかなり意識づけられましたが、それだけで事態を改善するのは難しいということもあり、法令遵守の一面だけでなく、社会的責任と企業倫理を重視する「インテグリティ・マネジメント」と呼ばれる概念が生まれました。
インテグリティの不足
2つ目の理由は、働き方改革の中で、従業員に不足している要素としてインテグリティが注目されるようになったことです。政府主導で働き方改革が進められたことによって、雇用問題が頻発するようになりました。このような問題が生じる大きな原因として、倫理観、つまりインテグリティの欠如が挙げられるようになったのです。
インテグリティの意識が高い企業であれば、顧客からの信頼を得やすくなります。結果として、健全な企業として自社をブランディングしていくことにもなるので、インテグリティが非常に注目されるようになりました。
経営層のインテグリティへの取り組み
3つ目の理由は、経営層が率先してインテグリティに取り組むことで、従業員それぞれも健全に企業経営を意識することにつながるからです。経営層が率先してインテグリティを実践する姿を見ることによって、従業員にも同じように行動したいというモチベーションが生まれます。結果として、会社全体としてインテグリティ・マネジメントが実践されるようになるのです。
コンプライアンスとの違い
インテグリティと混同されがちな概念として「コンプライアンス」という言葉があります。確かに似ている部分も多いこの2つの言葉ですが、厳密に言うとこの2つは異なるニュアンスを持つ概念です。今回の主題であるインテグリティを正しく理解するためには、コンプライアンスとの違いを把握しておくことも重要です。
コンプライアンスが「法令」や「社会規範」の遵守といった外的な規則を守ることにベクトルが向いているの対して、インテグリティの場合は、自分がきちんと正しく誠実であるか、自分自身の内面に反省の目を向けるようなベクトルを持った概念です。もちろんこの反省の中には、「自分や会社はコンプライアンスをしっかりと守れているか」といったことも含まれます。
コンプライアンス遵守はもちろん大切なことですが、その動機が「違反することによって社会的制裁を受ける」のような受動的なものである場合、「バレなければ何をしても良いのか」「法令で禁止をされていなければ不正を働いても良いのか」などの疑念が生じてしまいます。
単にうわべだけでコンプライアンスを守るのではなく、コンプライアンスを遵守するための精神を持つためには、そもそも各個人がインテグリティの意識を持つことが必要なのです。
インテグリティ浸透のメリット

ここまで見てきてもわかるように、インテグリティは健全な企業運営を行うために欠かせない要素です。経営陣がインテグリティの精神を持ち合わせているかによって、その企業が社会に貢献できる企業として成長するかどうかが決まると言っても過言ではありません。社会から本当に必要とされる企業になるためにインテグリティの重要性を理解することが大切です。ここでは、インテグリティが企業に与える3つの主なメリットを改めて見てみましょう。
コンプライアンスを遵守する従業員が育つ
従業員は、経営者が掲げた企業理念に基づき行動をします。つまり、経営者がインテグリティを持ち、コンプライアンスを遵守する行動を率先して行うことによって、従業員たちもそれを道標として正しい方向に進むことができるのです。
コンプライアンス遵守が企業文化として浸透し、インテグリティが高い人材が増えることによって、新入社員も含めてその文化が伝わり、結果として会社全体のインテグリティを高めることになります。インテグリティに重きを置いている企業は、自然と社会からも必要とされ、社会から存在意義を認められた企業へと成長していくことができるのです。
地域社会に貢献する組織の構築
法律や慣習が異なる国際市場で経済活動を行い、多様な価値観を持つ従業員が多いグローバル企業にとって、インテグリティは全世界共通の価値観として認識されるべき重要な要素です。
社内外にかかわらず、インテグリティの有無はコミュニケーション上のあらゆる場面で現れてきます。そのような点で、インテグリティを優先していると、どのような地域社会においても貢献のできる組織作りを行うことができます。ビジネス活動で地域社会に貢献できる企業は、より迅速に企業価値を高めて成長していくことができるでしょう。
企業イメージ・信頼の向上
経営者のみならず、従業員がインテグリティを高く持ち、地域社会に貢献することは、周囲からの会社のイメージと信頼の向上につながります。近年は、コンプライアンス遵守はある意味当然のことと考えられているので、その一歩先の取り組みとして、インテグリティを企業理念と結びつけることが可能です。
企業理念を元に行動することは、企業の特徴を浮き彫りにし、競合他社との差別化やブランディングにもつながっていきます。インテグリティの価値観を大切にすることで、人を大切にする姿勢が社会にも伝わり、企業のイメージと信頼を高めてくれるのです。
インテグリティを持つ人の特徴
冒頭で述べたように、インテグリティを定義するのは難しいとされています。しかし、経営者としてインテグリティを持つことは、企業を成長させる上で最も重要な要素の一つです。ここでは、インテグリティを持つ人の特徴と言えるものを3つご紹介します。経営者という観点でご紹介しますが、これは経営者にかかわらず共通していることでもあるので、採用の際など参考にできる部分も多いでしょう。
公正で正義感が強い
インテグリティを持つ経営者は、常に「何が正しいか」ということを基準に物事を判断します。正義感が強く、誰に対しても公正に物事を考えます。インテグリティを備えている経営者であれば、従業員の能力を公正に判断し、高い生産性を発揮できるようなチーム作りや環境づくりを行うことを優先します。自分の好みなどを優先するのではなく、その状況において何が最も効果的なのか、本質を見抜いて毅然とした態度で実行できるのが特徴です。
インテグリティを持つ経営者とは、いかなる時も自分の利益ではなく会社の利益を優先し、企業に関わる全ての人のこと考えて行動ができる人と言えるでしょう。
コンプライアンスの遵守
インテグリティが高い経営者は、法令遵守の意識を高く持ち合わせています。企業として、法令違反にあたるような案件には絶対に着手しないという確固たる意思を持って行動します。経営者がそのような意識を持っていれば、企業としても社会的責任を果たしながら企業活動を行うことができます。
従業員のたった一つの過ちが、会社全体を揺るがす不祥事になり得る今のような時代では、企業のトップがどのような価値観を持って行動しているかはとても重要です。経営者が高いインテグリティの下に行動をすることで、その姿勢が従業員にも伝わり、誠実な組織として社会にも認知されることでしょう。
倫理的な動機・行動をとる
コンプライアンスの意識と同様に、高い倫理観を持ち合わせていることも、インテグリティを持つ経営者の特徴です。利益を追求しつつも、相手を尊重し、トップとして道徳的観念を持つことが大切です。これが、取引先や顧客からの信頼へとつながります。
たとえ能力が高くても、人格に欠陥があれば問題を起こしてしまうかもしれません。インテグリティの高い経営者は、能力よりも人格が大事であることを認識し、人格に基づいた行動を優先します。
インテグリティ対策の事例

インテグリティに対する理解を深めるためには、実際に企業でどのように実践されているのかを知ることが有効です。ここでは、3つの企業を例に、インテグリティがどのように企業経営に生かされているかをご紹介します。
花王
日本を代表する企業の一つである花王は、「花王サスティナビリティ」というオリジナル冊子を作成しています。近年注目を集めている「サスティナビリティ」は、「持続可能」「持続可能な社会」などを意味する言葉です。自社が持続可能な社会づくりに取り組んでいるということをわかりやすく冊子にまとめることで、社内だけでなく社外にも周知をしています。このような活動を通じて、法令遵守と高い倫理観のもとで誠実な経営を行っていることをアピールしているのです。
また、コンプライアンスに関する通報や相談に対しても真摯に向き合う取り組みも行っています。このような取り組みを徹底することで、すべての従業員にとって平等な職場環境作りを行っているのです。
ブランディングに取り組むことで、結果としてさらなるインテグリティの実践にもつながっている良い例の一つと言えるでしょう。
伊藤忠グループ
日本の大手商社の一つである伊藤忠も、インテグリティに関する積極的な取り組みが行われています。伊藤忠では、大々的に「ITOCHU Mission」「ITOCHU Values」というものを打ち出しています。企業としてのミッションとバリューを明確に打ち出すことで、各従業員が向かうべき方向性を明確にしているのです。
また、企業基準行動として、誠実・情熱・多様性・挑戦・先見性を挙げています。これも、経営層から従業員に対して明確なインテグリティを示す一つの手法と言えます。
社内でインテグリティを徹底していくためには、経営層の率先した行動が欠かせません。それに続いて、従業員それぞれがどの方向に進むべきなのかを理解していることも必要です。伊藤忠の取り組みは、その両面をうまく進めている例の一つです。
ダイムラー
インテグリティは、日本企業よりも欧米企業で早く導入をされました。中でも、ダイムラーはインテグリティの考え方を積極的に導入した代表的な企業の一つとして知られています。ダイムラーでは、業務活動の基本としてインテグリティが位置付けられているとともに、インテグリティの実践を、会社の最重要課題として捉えています。
また、ダイムラーは「公正だと認められる倫理理念に従って企業活動が為される場合にのみ、経済的な成功が永続して可能になる」という考えを持ち、行動指針として従業員に示しています。さらに、従業員には義務感ではなく意思を持つようにと促しており、職場で実践されることを方針として定めている徹底ぶりです。まさにダイムラーは、インテグリティ・マネジメントを実前しているモデル企業と言えるでしょう。
インテグリティは企業経営に不可欠な要素
本記事では、近年企業に求められている「インテグリティ」の重要性についてご紹介をしました。
インテグリティは、現代の企業経営に欠かすことのできない要素の一つと言えますが、それは決して外から押し付けられるようなものではなく、各個人の心に根付いた倫理観なのです。SNSなどが普及し、企業の情報や動きが誰にでも見えやすくなった今だからこそ、インテグリティの重要性は増しています。
企業の経営層が高いインテグリティを持つことで、企業の健全も高まります。また、従業員も持つことで、お互いに助け合い、各自が率先して会社のために動けるような職場構築を期待することができます。
ぜひ今回の記事を参考に、将来の自社への信頼やブランディングにつながるインテグリティを持つためのヒントを得ていただければ幸いです。
おすすめ記事
