【wevox主催】「READYFOR」「Sansan」「Resily」3社の視点に基づいて、OKR導入や運用のポイントを徹底解説!セミナーレポート【後編:パネルディスカッション、質疑応答】BLOG
2021.6.10
2019年4月23日(火)に株式会社アトラエ本社にREADYFOR様(樋浦COO)、Sansan様(我妻マネジャー)、Resily(堀江代表)の3社が集まり、各社それぞれの視点から、OKRの導入や運用のポイントを解説するセミナーを開催いたしました。
前編では、Resily堀江代表による「情報提供セッション」をお伝えいたしました。今回はその後編として、3社による「パネルディスカッション」と「参加者からの質疑応答」についてレポートいたします。
司会進行:wevox平木様
OKR導入のポイントは「OKRの正解を決めずに、早くやって早く失敗すること」

左:READYFOR樋浦COO 中:Sansan我妻マネジャー 右:Resily堀江代表
ーまずはOKR導入の経緯を簡単にお教えください
READYFOR樋浦COO(以下、樋浦):弊社がOKRを導入したのは2018年7月からです。社員は100名くらいで、より「野心的な目標を立てていきたい」という流れからOKR導入に至りました。
Sansan我妻マネジャー(以下、我妻):弊社はOKRを2015年から導入しており、4年目に突入しています。社員数は現在およそ400名です。きっかけは代表の寺田が、「グーグルなどでOKRが成果を出している」と聞きつけたことです。
ー導入当初の状態や、従業員の方へどのように周知したかについてお聞かせください
樋浦:READYFORでは全社へ一気に導入しました。経営メンバーとマネージャーメンバーで、丸一日かけて全社のOKR設定を設定しました。初めてでOKRの立て方がわからない部分も多々ありましたが、結果的には予想していたものよりもかなり高い目標が設定されました。
その後マネージャーがメンバーにOKR設定の経緯を説明しつつ、「自分たちはこういう役割をもっているからどうしたらいいんだろうね」とリードしてもらいながら、チームOKRについて話し合いました。
我妻:Sansanでの導入は代表発信で、すぐに役員陣でカンパニーOKRを決めて、この3ヶ月間どこにテンションを張るか、キーワードを2〜3個設定しました。そこから役員が持っている事業領域にブレイクダウンしていく、という流れです。
ーResilyの堀江代表にお聞きしたいのですが、OKRの導入に関して色々な企業さんを見ている中で「こうしてしまうと失敗する」というものはありますか?
Resily堀江代表(以下、堀江):そもそも目標を定めるのは難しいんですよ。野心的な目標を立てて、想像を超えていくということ自体、抽象度が高いじゃないですか。メンバーからすると、「どういうこと?」となりますし、正直説明のしようが無いんですよね。ですので、「早くやって早く失敗しましょう」ということをお伝えしています。
弊社で関わる場合は、OKRの導入目的を明確化し譲れないポイントのみを押さえ、一般的なOKR運用の型を提供するにとどめています。運用の細かいルールはお客様の意思を尊重し、早期に肌感覚を掴んでもらうことを優先しています。そこに対し、壁打ち相手としてアドバイスをする形でファシリテートさせていただいています。
ーちなみにOKRを導入される企業において、従業員の方のOKRに関する知識はどれほどのものなのでしょうか
堀江:記事を読んでいる人はいれど、全体で見ればほとんど無いといっていいです。ですので説明する場合は本当にわかりやすい言葉で、
- 「目の前の業務を気持ちの良いものにするため、1週間に1個だけでいいからチャレンジしよう」
- 「毎日積み上げていくことがOKRで、それが会社の成長に繋がっていくからやっていこう」
ぐらいのレベルでブレイクダウンします。
OKRの1番のメリットは、目標の達成率が上がるということよりは、会社の情報が透明化されて、それを知った上でコミュニケーションをスタートできる文化が根付くことだと思っています。
OKRをあまり意識し過ぎず、パフォーマンスの最大化を考えることが大切

ーOKRの導入時にやって良かったこと、意識されたことはありますか
樋浦:OKRを決める過程において、メンバー全員を巻き込んだことは良かったと思います。OKRはやり方によってはトップダウンで動かすこともできると思うんですけど、弊社ではできるだけマネージャー以外のメンバーの意見を取り入れたかったんです。結果的に、OKR作成に至るプロセスに全員が納得できるような決め方ができたので良かったですね。とはいえ、運用しながら改善しなければいけなかった部分はかなりあったので、成功事例とまでは言えないです(笑)。
ー従業員の方には、事前にOKRに関する情報を伝えたりしたのでしょうか
樋浦:OKRを作るにあたって、マネージャーには全員に本を読んでもらいました。しかし、後から考えるとこれはやらなくても良かったと思っています。中途半端に知識を入れてしまったことで「60〜70%の達成でいい」「達成したら目標が甘すぎた」みたいな状況によって変わるものを必ずあてはまるし守らなければならないパッケージだと捉えて運用してしまう人が出てしまいました。
OKRがやり方が決まっているパッケージのように伝えすぎたということもあって、最近はずっと
- O=目的・ゴール
- KR=それを測る指標
ただそれだけだ、と伝えています。
その後にやったメンバーに関しては「目標管理のやり方を少し変えるよ」という形で、OKRに関する知識は無しで行いました。メンバーに伝えたことは、
- 全社の目標設定がどうなっているか見える化したい
- 高い目標にみんなでチャレンジしたい
といった内容です。あと「OKRのKRを達成したかどうかは人事評価に紐付かないよ」ということも、繰り返ししつこいくらい伝えました。
導入する側も「OKRとはこういうものだ」とやり方が決まったものとして取り入れるとうまくいかないので、「この人のパフォーマンスを最大化するためにどうしたらよいか」ということを考えて設定するのが1番良いと思います。
我妻:SansanがOKRを始めた当初は、国内にResilyのような素敵なツールが無かったんですね。
なので手軽にできることとして、トップがメッセージしているOKRから、ツリー構造でどのように部門と結び付いて自分たちがどうすべきか、ということを可視化させるためのものをパワーポイントで作っていました。評価との紐づけ方などに関しては、OKRを実際に使っているグーグルの方に話を聞かせてもらいながら落とし込んでいったりしましたね。
弊社OKRの運用について説明しますと、まず代表のOKRがトップに、その下に役員のものが書かれています。そこからブレイクダウンして、それぞれの部門でそこに結びつくために自分たちがやることを都度書き出していく感じです。これを3ヶ月サイクルでアップデートしながら運用しています。
また全体では、
- 2週間に1回、全社員が集う会議を設けて、個々に向けた話を代表からしてもらう(ここではOKRに関するものに縛られず)
- 3ヶ月に1回、振り返りと共有会をする
などをしていますね。
Winセッションをすることで生産性やエネルギーを高め、心理的な信頼関係が構築できる
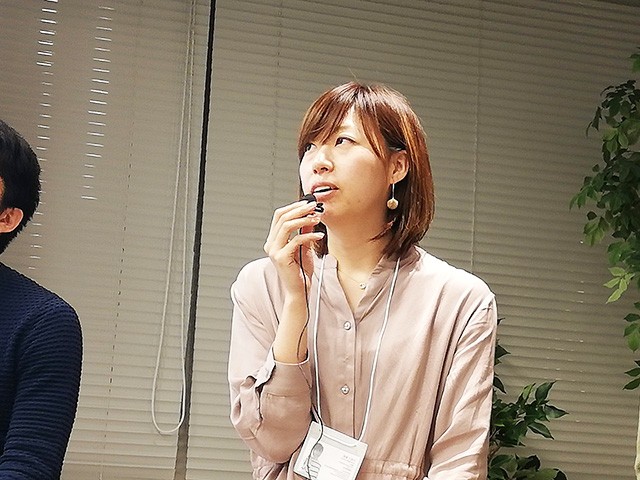
ーOKRを運用するうえで、進捗の確認方法や工夫していることがあればお願いします
我妻:Sansanでは先にお伝えしたとおり、3ヶ月に1度、全社員が集う場で振り返る運用をしています。日々の進捗確認については各部門にお任せしています。私のチームでは週次でミーティングを開催し、進捗を全員で確認できる場を設けています。
樋浦:READYFORでは、全社OKRとチームOKRの進捗を毎月1回、キックオフの時に共有、説明するようにしています。チームがいくつかあるので、必ず紙で印刷して進捗状況とマネージャーのコメントをつけて、紙を見れば各チームの状況がひと通り分かるようにしています。
また弊社では、個人OKRを全員決めていて、隔週でやっている1on1で上長が進捗状況を確認してフィードバックしながら、話し合いの中で自由に修正できるようにしています。あとは定期的にWinセッションをやることを推奨していて、毎週、その週のアクションでよかったところを褒めたりお互いの存在の承認をしていて、かなりの効果を感じていますね。
ー実は弊社のwevoxでもOKRを始めていてWinセッションをやっているんですが、会によっては盛り上がらず終わってしまいます。何かアドバイスをいただけますか
樋浦:弊社のWinセッションのやり方をお伝えしますと、だいたい人数は6〜7人、ひとり2分くらいで金曜日の夜に今週やったことをプレゼンします。その後1分半〜2分くらいで、スプレッドシートにみんなが褒めたいことを打ち込みます。そして順番に30〜40秒ずつくらい、ひたすら読み上げていくんです(笑)。
コツとしては、1人か2人褒め上手がいるとうまくいきます。
- あなたが居てくれるだけで幸せ
- あなたのこういう部分を尊敬している
など、褒め上手にどんどん感化されて周りの褒め方も毎週レベルが上っていくんですね。言われた側は気持ちよくなりますし、褒める側の恥ずかしさも消えていきます。
あとは時々違うチームに混ざってやるのもいいですし、お菓子なども用意しておくといいですね。弊社では1人200円のお菓子代を支給しているのですが、お菓子があると会自体の雰囲気が柔らかくなるのでおすすめです。
Winセッションをうまく回すと確実に生産性やエネルギーが高まりますし、心理的な信頼関係が構築されます。認めてもらえている人からだとフィードバックも聞きやすいので、そういった意味ではとても良い効果があると思いますね。
堀江:僕自身はけっこう頭が固い人間なので、褒めようと思っても「こうしたらもっと良くなる」と思ったら言ってしまうんですね。Winセッションに関しては、そういうのは絶対にNGです。本当に小さいことでもいいから深掘りして褒めてあげる。褒めまくって気持ちよく帰ってもらうのが大切です。
あとはメンバーと共有しているスプレッドシートに積極的に絵文字を入れるようにしていますね。それをするだけでもテンションが上がる雰囲気ができてきますよ。そのように雰囲気づくりを改善していくのも大切だと思います。
OKRの管理方法は、自社の課題やニーズにあわせて柔軟にカスタマイズする

ー最後にOKRの管理方法についてお聞かせください
樋浦:READYFORでは、チームごとに週次の定例ミーティングを実施しているので、そこで現在の状況の報告が上長にくるようになっています。個人OKRに関しては1on1の中で見るようにしています。
あわせて評価制度との紐づけで言いますと、OKRを作ってもらったときにここまで出来たらこれくらいの評価だよという期待値を上長が設定しています。
個人ごとに期待値を設定することで、目標を達成する満足感を感じてもらいやすくなりますし、自分に対する評価とOKRとを比較しながらコミュニケーションをとることが可能です。
まだ結果はこれからですが、これをしてから「OKRを達成するかしないか」ではなく、単純にパフォーマンスを見ていることが伝わり、評価に対する納得感が上がるのではないかと思います。
我妻:Sansanでは大半Resilyを使っていますが、人事部門などはまだ未導入で、チームレベルでスプレッドシートを使って運用しています。おおまかには、
- 役割分担の決定
- 進捗確認
- 軌道修正
などに活用しています。
OKRを進める上でうまくいっていないものがあれば、リーダーに報告を上げつつ都度チューニングをしていく形です。
また評価に関わる部分では、弊社でもREADYFORさんと同じように、個人OKRの落とし込みのときに「目標達成6〜7割」を気にし過ぎてしまうという声はありました。
そこで、評価のあり方を「OKRをどれだけ達成できたか」ではなく、「チームとして掲げているOKRに対してあなたはどのように貢献できましたか」という評価に切り替えていきました。弊社ではこれを「アチーブメント評価」と名付けています。
そうすると個人として設定したものに縛られなくなっていきますし、途中で向き合うものが変わったとしても、その中で貢献できたものをしっかりと評価することも可能です。
堀江:自分たちも自社のツールを使っているのですが、戦略や判断に至った経緯がわかるドキュメントツールみたいなものも使っています。そのリンクをOKRのところに貼り付けたりする感じです。各部門の最新の動向がわかる表だけはResilyツール内に入れて、その他のダッシュボードは別で用意するなどして切り分けています。
野心的な目標を実現するには、挑戦を否定されない環境を整えることが重要

ーここからは、会場の方からも質問を受け付けたいと思います
【質問1】「野心的な目標を掲げる」を実現するには、これまで通りの仕事の仕方ではダメだと思うんですが、どのような仕掛けを作っていくことが必要なのでしょうか
我妻:野心的な目標を、ということから始まったわけではないのですが、Sansanでは「変化を恐れず、挑戦していく」というバリューズをキーワードとして持っています。
課題に対して主幹部門のメンバーじゃない人たちが新たに出してくれた声を認めるなど、影響力のあるメンバーが、日常の中でいかに枠を超えて伝えていけるかが重要だと考えています。
樋浦:実は、今後は「野心的な目標」という考え方にウェイトを置かないようにしようと考えています。やってみてわかったことですが、やり方を変えるような野心的な目標は、ビジネスモデルを変えることができる人とか、たくさんの採用ができる人とか、一定の権限がある人でないと難しいじゃないですか。一定決まった役割を果たすことに注力している人は「野心的」であるよりも着実に成長してもらい、より大きな価値を発揮してもらえるようになることの方が大事だと思います。
そういったメンバーには成長のスピードを速めるような方向で野心的な目標を立ててもらうのがいいのかなと考えています。

【質問2】OKRを決めたときはテンションが上がり納得度が高いのですが、実際にやるとなると業務オペレーションもあるし、かなりハードルが高いと感じてしまいます。個人OKRを設定していない場合、どのようにフィットさせていけばよいのでしょうか
樋浦:ゴールまでを想像すらできてない目標は実現が難しいと思いますね。弊社でも最初はマネージャーにできるだけ自由に立ててもらおうと、現状の利益率やユニットエコノミクスを考慮せずに作ってもらっていたのですが、結局うまくいきませんでした。メンバーにはトップがある程度道筋をイメージした計画に対して、いかに上回るかを考えてもらう方が良い、というのが今の考えです。
堀江:OKRをワークさせるために、外部の力を借りるということを積極的にやっていますね。採用したい人たちをどんどんスラックに入ってもらって指摘をもらいます。できるだけ情報をオープンにして、経営合宿のように全社員で自由に話せる場を作るようにしています。
【質問3】OKRに付いて来てくれない人がいる場合に、どうすれば同じ方向を向いてもらえるのでしょうか
樋浦:READYFORでは、会社で決めた制度的なものなのでまずは取り入れてみてほしい、という形で伝えています。でも前向きに取り組んでもらうことは大切なので、どう巻き込んでいくかも含めてメンバーに対して丁寧な説明は欠かせません。ポジティブなフィードバックがかかるようにしたり、Winセッションのような効果がわかりやすいものを通じて、少しずつ広めていくのが良いのではないでしょうか。
我妻:Sansanも同じ話になってしまうんですけど、OKRってトップ起案で始まったりするので、そこにメンバーが違和感を覚えたりする場合は、人事や上長が自らの言葉で背景や狙いを伝えていくことが大切だと思います。
堀江:樋浦さんと同じで、Winセッションで気持ちよくなっている人の顔を見せる、ということが1番効果があると思いますね。Winセッションは参加している人が本当に楽しそうに帰っていくので、これを見てると羨ましくなるはずですよ。
OKRの型にとらわれず柔軟に運用することで、パフォーマンスの最大化が実現する
ここまで、OKRの導入や運用のポイントについて「READYFOR」「Sansan」「Resily」の3社によるパネルディスカッションと質疑応答の内容をお伝えしました。
いずれの組織においても「OKR」というツールを使っているのは一緒ですが、その運用や管理の方法はそれぞれで工夫されていました。OKRをうまく活用するポイントは「OKRの型にとらわれ過ぎないこと」です。失敗を恐れず、課題に1つひとつ向き合いながら組織のパフォーマンス最大化を実現しましょう。
まずはWinセッションからスタートしてみるのもおすすめですよ!
おすすめ記事
