目標管理(MBO)とは?メリットやデメリット、OKRとの違いを紹介BLOG
2022.12.9
結論から言うと、MBOとOKRの違いは人事評価に活用するかどうかです。MBOでは企業の生産性を高めるのとあわせて、目標の達成度合いを従業員の評価にも活用します。一方で、OKRが目指すのはあくまで企業の生産性向上で、人事評価には直結しません。これがMBOとOKRの違いです。
今回はMBOのメリットやデメリット、OKRとの違いや共通点についてさらに詳しく紹介するので、MBOについて大まかに理解しましょう。
目標管理を効果的に行いたい企業におすすめの資料を無料で公開していますので、ぜひこちらもご確認ください。
目次
1. 目標管理(MBO)とは?簡単に概要を解説
2. OKRとMBOの違いを詳しく解説
3. 目標管理(MBO)のメリットとデメリットを確認
4. 目標管理(MBO)を導入する前にすべきこと:現状を分析する
5. MBOを導入した企業3社の事例を紹介
6. OKRとMBOの違いを理解して、 現状を分析した上での目標管理をしよう
7. 現状を分析した上での目標管理を!
目標管理(MBO)とは?簡単に概要を解説

目標管理(MBO)とは、簡単に言うと「目標によって組織を管理すること」です。MBOはManagement by Objectivesを略した言葉で、直訳すると「目標による管理」となります。
MBOは経営学者で「現代の経営」の著者ピーター・ドラッカーによって提唱されたマネジメント手法です。企業が目指す目標に向けて従業員自身やチームで目標を設定して申告し、進捗を管理しながら生産性を高めます。
MBOは「目標を管理する手法」ではなく「目標を通じて組織を管理する手法」である点がポイントです。
従業員が自分で目標を決めるセルフマネジメントによる方法のため、自主性を持って目標の達成に取り組めます。
MBOはタスクにかけた時間や労力、成果が可視化されるフレームワークで、従業員のモチベーションアップと業務の効率化につながるのが特徴です。従業員のモチベーションがアップすれば、企業としての生産性の向上も期待できるでしょう。
OKRとMBOの違いを詳しく解説

同じ目標管理の手法であるOKRとMBOにはどのような違いがあるのか、見てみましょう。
| OKR | MBO | |
|---|---|---|
| 目的 | 生産性の向上を目指す | ・生産性の向上を目指す ・従業員の評価に利用する |
| 個人目標が共有される範囲 | 社内全体 | 限られたメンバー |
| 評価の頻度 | ・1週間~1ヶ月に1回程度 ・継続的パフォーマンス管理 | ・半年~1年に1回程度 ・半期振り返り、評価面談 |
| 計測方法 | 定量的に計測 | 定量的・定性的に計測 |
| 理想的な目標の達成度 | ・60%~70% ・ムーンショット ・ルーフショット | ・100% ・人事評価で判断可能 |
それぞれの項目について詳細を紹介します。
OKRについては以下の記事で詳細を紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。
OKRとは?Google採用の目標管理フレームワークを導入事例を交えて紹介。KPIやMBOとの違いも解説
目的
MBOとOKRの目的は企業の生産性を高めることです。両者の目的は同じですが、人事評価に活用するかどうかが違います。
- MBO:目標の達成度合いを従業員の評価に活用する
- OKR:簡単には達成できない野心的な高い目標を設定して、人事評価とは切り離して考える
MBOでは企業の生産性を高めるのとあわせて、目標の達成度合いを従業員の評価にも活用します。目標の達成度が高ければ報酬の額が上がるといったように、個人の金銭的な評価に直結するのが特徴です。
MBOでは目標の達成度合いが金銭的な評価につながるため、低すぎる目標設定になる可能性があります。
ドラッカーが提唱したMBOは、マネージャーが従業員をマネジメントする際に目標を用いて企業目標と従業員が設定した目標を整合させて生産性を高める管理手法として普及しました。
しかし日本では、90年代の後半に成果主義を背景として人事評価のための管理手法として広まりました。当時の日本は経済の低迷からコストカットが重視され、人件費を抑えつつ効率的に評価する仕組みとして採用が進み、当時の基本コンセプトのまま現在も活用される場合が多くあります。
OKRが目指すのは企業の生産性の向上で、人事評価ではありません。簡単には達成できない野心的な高い企業目標を設定して、目標達成を目指すものです。個人の評価のために設定される目標とは出発点が異なります。
OKRのポイントは企業と部門やチーム、従業員の目標を連動させて可視化し、組織全体としての方向性を一致させることで、組織の総合力を発揮してミッションやビジョンの実現を図ることです。そのため、人事評価とは切り離してOKRを設計します。最終的なゴールが企業全体としての目標達成なので、個人の評価には直結しません。
目標達成度に応じて個人を評価するMBOは評価判断が客観的かつ容易で、従来の経済成長期における年功序列といった曖昧な能力評価から、1990年代後半のコスト削減、効率化という日本企業のニーズにマッチしたため、本来のコンセプトに加えて評価基準として用いられたのです。
個人目標が共有される範囲
MBOで目標が共有される範囲は、上司などの限られたメンバーのみです。従業員の評価の意味もあるMBOでは、上司が直接確認した方が社内全体で共有するよりも成果がわかりやすいため、社内全体ではなく一部の限られたメンバーのみに個人目標が共有されます。
OKRでは、従業員個人やチームの目標が企業全体で共有されます。OKRのゴールは企業としての目標達成で、成果を確認するには他の従業員やチームの動きや状況を把握する必要があります。
全員の目標と成果指標を透明化すれば誰が何をやっているか理解でき、社内でのコミュニケーションの促進が可能です。コミュニケーションが促進されれば、業務の効率化にもつながります。
評価の頻度
MBOでは半年~1年に1回程度の頻度で評価が行われます。人事評価の意味合いも兼ねるMBOではノルマの達成度合いを評価する場合もあり、頻繁な評価ではなくある程度の期間を空けて評価をする方が向いているのです。また、MBOが考えられた時代は、現在ほど事業環境の変化が大きくはなく、6ヶ月後も取り組んでいることに大きな変化があることは限定的でした。
OKRでは1週間~1ヶ月に1回程度と高い頻度で評価が行われます。評価頻度が高いのは、事業環境の変化に応じて、現状を把握してこまめに軌道修正する必要があるからです。
軌道修正のためには、詳細な情報の把握が欠かせません。OKRにおける目標は、やってみなければ、どれほど達成に近づけるか分からないため、実態とかけ離れてOKRが形だけにならないよう、以下のような取り組みが行われます。
- 週初めに行うチェックインミーティング
- 週末に行うウィン・セッション
課題や成果を共有する会議体の雛形がデザインされており、パフォーマンス評価とあわせて対話する制度が組み込まれているのがOKRです。
計測方法
MBOでは定量的な評価と定性的な評価が組みあわせて行われ、評価方法は企業ごとに決められています。たとえば「製品に関する知識を高める」など、数値にできない評価基準があるのが特徴です。
定性的な評価では、上司の主観に左右されて結果が変わる側面もあります。運用する際には、主観が部下の評価に影響しないように注意しなければいけません。
OKRでは定性的な目標とともに定量的に達成が確認できるよう評価指標が併記されます。OKRの構造は、目標として定性的なものを立て、その目標を達成したと確認できたり、進捗を測定するために設けられているのが定量的な評価です。
OKRでは以下のように厳格に数字で評価が行われます。
- 3ヶ月以内に5名の内定候補者を獲得する。その採用コストを10%削減する
- 3ヶ月以内に昨年トライアル契約した既存顧客20社に対し納品数を30%増やす
数字で結果が求められ、客観的に達成度合いがわかる仕組みです。数値で評価するのは、企業の成長や生産性の向上のためです。
- MBO 製品に関する知識を高める
- OKR 製品知識を高め、新規20商談のうち10商談で製品評価案件(PoC)を獲得する
達成度合いは数値化されますが、目標の達成度が100%であろうと50%であろうと評価には響きません。人事評価と結びつけると従業員が評価を恐れて達成しやすい目標だけを立ててしまう懸念があるからです。力の出し惜しみなど企業も従業員も成長が図れず、中長期的に事業が縮小します。人事評価の結果が全体的に良いにも関わらず、多忙だが業績や給与が伸びていない場合は危険です。
理想的な目標の達成度
OKRにおいて求められる達成率は60〜70%です。100%達成できる目標は簡単すぎる、余力を残しており生産性が低いとみなされます。
OKRでは野心的な目標を設定する必要があるため、達成の自信度が5割くらいの目標が好ましいのです。達成できるか五分五分の可能性の目標は、どうすれば良いかと創意工夫が促され、結果として企業や従業員の成長を最大化します。
人事評価と結びつけて考えられるMBOでは、立てた目標の100%達成が求められます。100%とすることで成果主義のもと原点評価を実施しやすく、人件費を抑える目標が達成できます。仮に、100%を超えた場合は、そもそも簡単な目標であった、実力以外の環境が良かったから、運が良かったからなどの理由を付けることができます。
また、評価するための目標であるため、途中で変更すると評価しにくいとの判断から目標自体を状況に応じて変えるプロセスが設計されていない場合もあります。新規より既存顧客が成果を出しやすい事が分かっても、期初に設定した目標はそのままで、実際には既存顧客に対する業務を行って評価のタイミングを迎えることもあります。
90年代にドラッカー自身もMBOが人事評価と結びついたことで効果的なマネジメント手法では無くなってしまったと記しています。目標管理と人事評価を結びつける際には、運用方法などを設計し、評価者と被評価者が制度を理解して適切に活用できなければ、本来の目的と効果を得ることは難しいのです。
▼こちらも併せて読みたい▼

MBOからOKRに変えたことで、自律的にアクションする組織づくりに成功した事例
従来のMBOでは会社が目指しているところがわからないということに課題を感じ、OKRと専用ツールResilyの導入を決めた大日コンサルタント様の事例です。
目標管理(MBO)のメリットとデメリットを確認
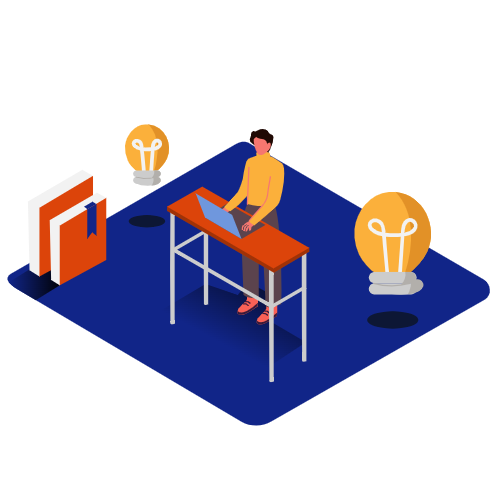
MBOを効率的に取り入れるなら、メリットとデメリットを理解しておく必要があります。
メリットとデメリットについて詳しく紹介するので、メリットを生かしデメリットをカバーするための参考にしてみてください。
目標管理(MBO)のメリット
MBOのメリットは、以下の通りです。
- 従業員のモチベーションアップや能力のアップにつながる
- 従業員が自己管理できるようになる
- 企業全体として方向性を統一できる
- 目標を基に振り返りを行い具体的な対策ができる
- 企業目標が達成できる可能性が高まる
それぞれについて詳細を確認しましょう。
従業員のモチベーションアップや能力のアップにつながる
MBOは従業員のモチベーションアップや能力アップにつながるのがメリットです。
MBOでは自分で目標を設定できるため、「やらされている」という感覚に陥りません。
会社やチーム、上司が目標を決める場合、従業員は決められた目標を遂行するだけになります。自主的な行動でないと、目標を達成しても「会社に利益をもたらしている」「会社に貢献している」という実感が得づらく、モチベーションが高まりません。
自分で目標を立てて自主的に取り組めばモチベーションアップにつながり、目標を達成するために熱心に取り組めます。熱心に業務に取り組めば、能力アップも可能です。
MBOでは従業員自身が目標達成のための管理を行うのとあわせて上司も進捗を管理し、1on1などでフィードバックをもらえます。上司に管理される安心感と自分が評価されているという充足感が得られるのも、モチベーションアップや能力アップが期待できる理由の一つです。
従業員が自己管理できるようになる
MBOを採用すると、従業員が自己管理できるようになります。
企業が目指す目標に向けて従業員自身やチームで目標を設定して申告し、進捗を管理しながら生産性を高めるのがMBOです。目標を達成するためにも従業員自身で進捗を管理しなければいけません。
従業員自身が立てた目標に向けて「進捗を自身で管理する」という意識を持って取り組めば、自己管理ができるようになります。
企業全体として方向性を統一できる
MBOでは従業員自身やチームが企業目標を元に目標設定を行います。
各自が自身の課題を元に目標を立てるのではなく、企業目標を達成するための目標を立てるため、同じ方向性を目指した取り組みが可能です。
立てた目標を上司に相談する段階で、適切でない場合は見直しも行われます。全員が同じ目標の達成を目指せば、企業全体としての方向性の統一も可能です。
目標を基に振り返りを行い具体的な対策ができる
MBOには目標を基に振り返りを行い、具体的な対策ができるメリットもあります。MBOにおける目標は数値などの客観的に進捗判断できる内容で設定されれば、透明性が高まるのが特徴です。
従業員に評価までのプロセスがわかり、目標の達成度を客観的に把握できれば、振り返りが行いやすくなります。振り返った内容を基に対策を立てれば、具体的な対策が可能です。
企業目標が達成できる可能性が高まる
MBOを取り入れれば企業目標が達成できる可能性が高まるのもメリットです。
上記で確認したように、従業員のモチベーションアップや能力アップが叶えられれば、企業自体の生産性も高められます。
振り返りを行って具体的な対策が立てられれば、目標が達成できなかった問題点を取り除ける可能性もあるでしょう。
MBOのメリットを知れば、効率的な運用が可能です。
MBOのデメリット
MBOにはメリットだけではなく以下のようなデメリットもあります。
- 評価に関わるため目標の設定が低くなるケースがある
- 企業目標が元になるため従業員の自由度はそこまで高くない
- 定性的な評価を取り入れると上司と部下で判断が食い違う可能性がある
- 目標の公開範囲が狭くチームワークが低下する可能性がある
- 目標管理の目的が人事評価のみに偏る危険性がある
- 評価者の負担が増える
それぞれのデメリットを詳しく確認して、カバーできるようにしましょう。
評価に関わるため目標の設定が低くなるケースがある
MBOの目標の達成度合いは人事評価に関わるため、目標の設定が低くなるケースがあります。
目標が達成できなければ報酬が低くなるのなら、達成できないような高い目標は立てられません。
従業員にとって達成しやすい目標を立てれば、企業にとっては生産性の低い目標設定になる可能性があります。生産性の低い目標は、達成できたとしても企業の生産性にはつながりません。
それを10年、20年と続けてしまう場合もあります。現在の自社の制度は何年前に設計されたのか、実態と合っているのか、制度にも耐用年数があることにも注意が必要です。
企業目標が元になるため従業員の自由度はそこまで高くない
MBOでは企業目標を元に従業員やチームの目標を立てる必要があり、従業員の自由度はそこまで高くありません。
従業員自身が取り組みたい課題があっても、企業の目標に従っていなければ別の目標を立てる必要があります。
本当に自分が達成したいと感じる目標でなければ、従業員のモチベーションが高まらない可能性もある点に注意しましょう。
定性的な評価を取り入れると上司と部下で判断が食い違う可能性がある
定性的な評価を取り入れると、上司と部下で判断が食い違う可能性があるのもデメリットです。
たとえば「製品に関する知識を高める」という内容を評価する場合、従業員は知識が高まったと判断しても上司はまだ足りないと感じる場合があります。
定性的な評価は客観的に判断しづらい点もあるため、明確な基準が設けられるよう注意しましょう。
目標の公開範囲が狭くチームワークが低下する可能性がある
MBOでは目標の公開範囲が狭く、チームワークが低下する可能性もあります。
MBOには人事評価の側面があることから、上司と部下といった限られたメンバーだけで情報が共有されます。OKRのように社内全体の動きが把握できるわけではありません。
透明性が低くなり、部分最適化されることで企業全体としてのチームワークにはつながらないケースが見られます。
目標管理の目的が人事評価のみに偏る危険性がある
目標管理の目的が人事評価のみに偏る危険性があるのも、MBOのデメリットです。
MBOは本来は会社のトップやマネージャーが従業員をマネジメントする目標による管理手法ですが、日本では人事評価の手法として広がったという背景があります。
目標を通じて組織を管理する手法ではなく、人事評価の手法としてMBOを活用すると、本来の目的である企業の生産性を高めるためには役立ちません。
評価者の負担が増える
MBOを導入すると通常業務に加えて以下のような評価のための業務が増え、評価者への負担も増えることが想定されます。
- 部下の目標のチェック
- 部下との定期的な面談
従業員の目標が企業目標に合っていなければ意味がないので、上司が目標をチェックする必要があります。
目標の達成度合いを評価するには、部下との定期的な面談も必要です。
MBOを導入する際に評価者の負担をできる限り減らす方法としてツールを活用するなど、対策を考える必要があります。
▼こちらも併せて読みたい▼
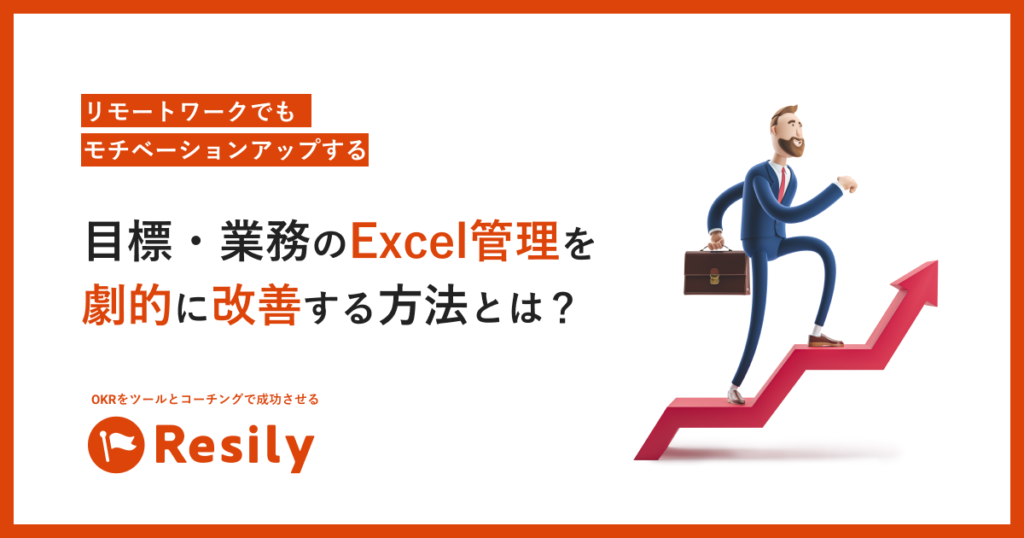
目標管理はエクセルでやるな!?専用ツールで実現する理想の働き方とは
目標の数値がズラッと並んだエクセル・スプレッドシートを作ったor送られてきた経験はないでしょうか?そのような管理方法では逆効果になってしまうかもしれません。
目標管理(MBO)を導入する前にすべきこと:現状を分析する

目標管理(MBO)を導入する前にすべきことは、現状の分析です。現状が理解できれば、MBOを用いる理由をはっきりさせられます。MBOを用いる理由がはっきりしていないと、実際に導入した後に運用し続けるかどうかの評価基準を持てません。
現状を分析して「これならMBOによって改善できる」と判断できたときだけ、MBOを導入しましょう。
目標管理(MBO)の5つのステップ
目標管理(MBO)は、以下5つのステップで行われます。
- 組織、チームごとに目標を設定し、従業員に共有する
- 従業員個人の目標を設定する
- 目標達成のために活動する
- 結果を評価する
- 制度そのものを評価する
以下で詳しく紹介します。
1. 組織、チームごとに目標を設定し、従業員に共有する
1つ目のステップは、組織、チームごとの目標設定と共有です。
目標はあいまいなものであってはいけません。全体として具体的な目標があったほうが、従業員がどのような目標を立てたらよいかわかりやすくなるためです。
目標を共有するときには、目標の達成によって得られる成果や意義を従業員に想像してもらいましょう。何のために行うのか、何を目指すのかをはっきりさせれば、従業員が業務に積極的に取り組めます。
2.従業員が、個人の目標を設定する
2つ目のステップは、従業員による各自の目標設定です。
組織の目標と同じく、従業員の目標も具体的で客観的に評価できるものでなくてはいけません。たとえば「多くの会社に営業する」ではなく、「新規100社に営業する」など数字で表すと、定量的にチェックしやすくなります。
従業員が目標を設定したら、目標に対して上司が以下の2点をチェックしましょう。
- 部下の設定した目標の方向性が、企業の方向性と一致しているか
- 部下にとって目標は達成できそうな難易度か
新規顧客に訴求するキャンペーン施策があるのか、達成を目指す期間内に100社の商談を創出できるのか、商談の量を高めるのか、質を高めるべきなのかなど、
目標が正しく設定できれば、MBOを効果的に運用できます。
3. 目標達成(MBO)のために活動し、進捗を管理する
第3のステップとして、目標達成のために従業員がそれぞれ活動しましょう。
目標を達成するには、上司とともに進捗を管理する必要もあります。進捗の管理には定期的に面談の機会を設けるのがおすすめです。
4. 結果を評価する
期末になったら、従業員ごとのMBOの結果を評価します。
基本的に結果は以下の2つのステップで行いましょう。
- 従業員自身が評価する
- 従業員の結果や評価を上司が評価する
従業員と上司それぞれで、どれだけ目標を達成できたかを判断します。
5. 制度そのものを評価する
最後にMBOの制度そのものを評価します。制度そのものについてPDCAを回すわけです。
具体的には以下の点をチェックしましょう。
- 目標管理制度は組織の目標達成につながったか
- 面談のタイミングは適切であったか
制度そのものが上手くいっていなければ、効果が期待できません。
MBOを導入した企業3社の事例を紹介
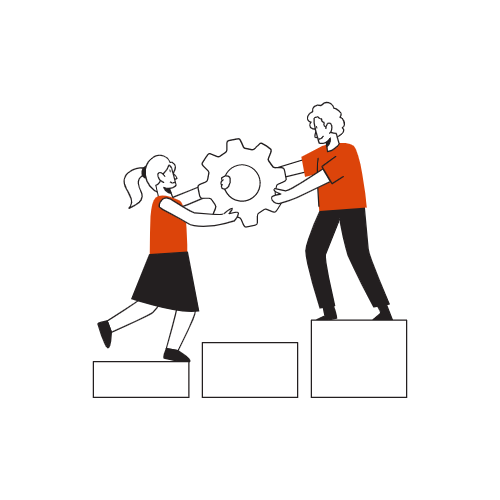
事例を見れば効率的な運用方法を知るきっかけにできます。実際にMBOを導入し、運用をしてきた3社の事例を見ていきましょう。
グリー株式会社
グリー株式会社はMBOの運用に成功している企業の1つです。
グリーがMBOを成功させるにあたって取り組んだ施策は2つあります。
- 目標の達成基準を5段階にする
- 定期的に1on1ミーティングでフィードバック
それぞれについて詳細を紹介します。
1.目標の達成基準を5段階にする
まず上期(6〜8月)と下期(12〜2月)に各社員が目標設定を行います。目標数は半期でだいたい5〜6ほど設定。目標設定が終わったら、それぞれに重要度の指数を入れていきます。重要度の高いものから優先的に取り組むためです。
さらにそれぞれの目標に先にも述べた5段階の達成基準を入れていきます。たとえば「2,000万円の売上目標」に対して結果が1,000万円であれば達成度は2〜3となるわけです。
目標を立てるだけでなく、結果を明確な達成度数で表すことで評価もしやすくなります。
2.定期的に1on1ミーティングでフィードバック
1on1ミーティングで行うのは「すり合わせ」です。前項の5段階の達成度は従業員側でいったん評価を出して、その後上司との面談で細かく詰めてすり合わせをします。こうした上司と部下のすり合わせの場を定期的に行います。その他、目標に対しての進捗確認や、適宜フィードバックを行うのです。
MBOにおいて、上司と部下の話し合いの場は欠かせません。目標管理手法は一歩運用方法を誤れば従業員のモチベーションと向上心を下げる可能性もあります。1on1ミーティングのは、部下のコンディションを把握し、軌道修正を行う良い機会です。
グリーは話し合いの場を定期的に持つ方法でMBOの運用を成功させました。
株式会社ユー・エム・アイ
株式会社ユー・エム・アイは1971年に創業しました。製造業にマーケットを置き、主にプラスチックやアルミ製品を取り扱っています。
MBO導入の背景には、現場で活躍していた従業員が管理職になるかたわら、優秀な人材は必ずしもマネジメント能力に優れてはいないという課題がありました。MBOの導入によって「人材育成の環境を整える」ことを目的としたのです。
それに付随して、従業員側に「目的を意識した業務の遂行をしてもらう」というのも、もう一つのターゲットでした。
MBO導入後は、6ヶ月に1回のスパンで目標設定とフィードバックを行っています。
ユー・エム・アイがMBOに取り入れた工夫は、「1on1を2回行う」ことです。1回目の1on1は直属の上司と「目標の達成度に応じた成果評価」を行います。
2回目の1on1は、「部下の本音を吸い取る」ことを目的として人事考課の担当と行います。普段接する直属の上司には、やはり本音は話しづらいものです。2回目の1on1でじっくりと部下と話し合い、部下の気持ちに特別な配慮をするのです。
この工夫は功を成して、MBOに対する従業員の満足度は高く、モチベーションも向上しました。
効率的な目標設定のために確認したいOKRとMBOの共通点
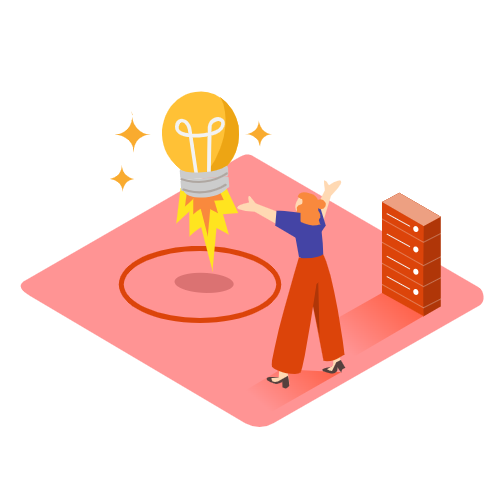
効率的な目標設定のために、OKRとMBOの共通点を確認しましょう。
両者の共通点は以下の通りです。
- 従業員自身が目標を決める
- 従業員自身が目標を達成できるよう自主的に業務を行う
- 押し付けられる意識がないためモチベーションが高められる
- 上司は部下のサポートを行う
OKRもMBOも目標を基に組織を管理する手法で、上層部が目標を決めるのではなく従業員自身が決めるのが特徴です。自分で決めた目標が達成できるよう、従業員が自主的に業務を行います。
従来の日本企業では、上層部が目標を決めて管理するやり方が行われてきました。
決められた目標だと「押し付けられている」「やらされている」という意識が生まれ、モチベーションが下がってしまいます。OKRやMBOなら自分で目標設定ができるため、モチベーションが高まるのがメリットです。
自主的に業務を行えばセルフマネジメントの能力も身に付き、業務に関する能力のアップも期待できます。
上司が行うのは、部下のサポートです。「目標が企業目標に沿ったものになっているか」「達成度合いはどれくらいか」を定期的に確認して、部下がスムーズに業務に取り組めるような対応をします。
上層部が目標を決める場合、上層部が部下に対して圧力をかけるケースも見られます。
現場を無視した高い目標や過度にストレスを感じながらの仕事では、成果が残せないのも無理はないでしょう。従業員の自主性を重んじて、モチベーションを高めて仕事に取り組めるようにするのがOKRやMBOです。
OKRとMBOの違いを理解して、 現状を分析した上での目標管理をしよう

また、企業の生産性は高められません。
OKRとMBOの性質をそれぞれ生かすには、両者を併用してデメリットを補う方法もあります。
企業の生産性を高めるOKRの目標例をチェックしたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
OKRの目標例を4つの企業から学ぶ【失敗しないための3つのポイントも紹介】
OKRとMBOを併用する手法の例
OKRとMBOを併用する手法の例を見てみましょう。
- OKRとMBOそれぞれの目標を設定する
- OKRの要素のいくつかを人事評価に利用する
一つ目としてOKRとMBOそれぞれの目標を設定する方法が考えられます。OKRの目標は人事評価には影響しない、MBOの目標は人事評価に活用すると事前に分けておけば、低い評価がつかないよう低い目標を設定する心配がありません。
OKRで野心的な目標を設定し、MBOで確実に達成すべき目標を設定すれば、従業員も安心して業務に取り組めます。
もう一つが、OKRの要素のうちいくつかを人事評価に利用する方法です。たとえばOKRはチームの評価にのみ用いて、個人の評価はMBOを基に行うなどの方法が考えられます。
現状を分析した上での目標管理を!

今回紹介したように、目標管理(MBO)とは「目標によって組織を管理すること」です。
MBOには、以下のようなメリットがあります。
- 従業員のモチベーションや能力がアップする
- 従業員が自己管理できるようになる
- 企業全体として方向性を統一できる
- 目標を元に振り返りを行い具体的な対策ができる
- 企業目標が達成できる可能性が高まる
一方でMBOには以下のようなデメリットもあります。
- 目標の設定が低くなるケースがある
- 従業員の自由度はそこまで高くない
- 上司と部下で判断が食い違う可能性がある
- チームワークが低下する可能性がある
- 目標管理の目的が人事評価のみに偏る危険性がある
- 評価者の負担が増える
MBOを組織に導入する際には、まず現状を分析し「何のためにMBOを導入するのか」を確認しておくことが重要です。
目標管理は以下5つのステップを踏んで進められます。
- 組織、チームごとに目標を設定し、従業員に共有する
- 従業員個人の目標を設定する
- 目標達成のために活動する
- 結果を評価する
- 制度そのものを評価する
まずは組織の現状を分析して、目標管理が組織や従業員にどのような影響を与えるのかを想定することからはじめてみてください。
▼こちらも併せて読みたい▼
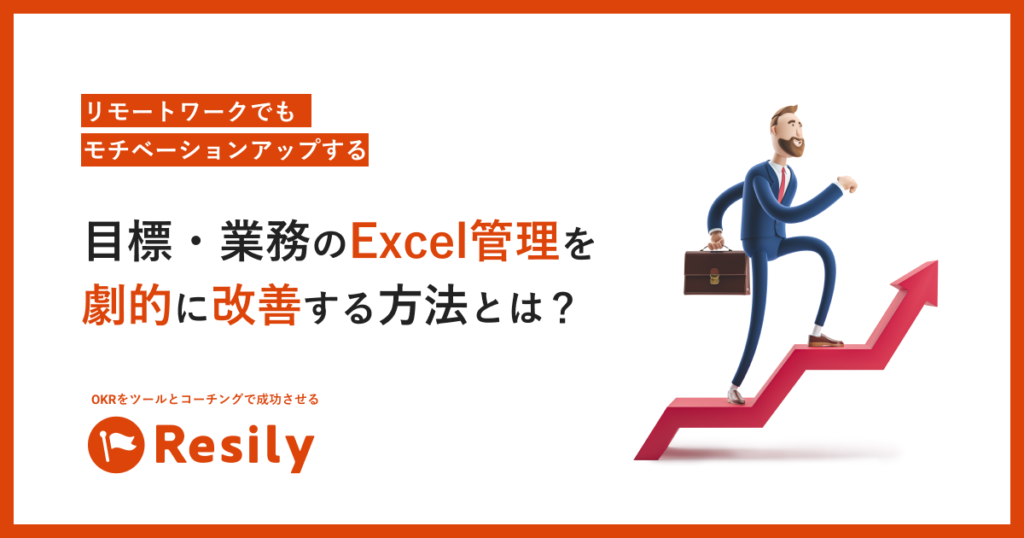
目標管理はエクセルでやるな!?専用ツールで実現する理想の働き方とは
目標の数値がズラッと並んだエクセル・スプレッドシートを作ったor送られてきた経験はないでしょうか?そのような管理方法では逆効果になってしまうかもしれません。
目標管理(MBO)に関するよくある質問
目標管理(MBO)とは?
目標管理(MBO)はManagement by Objectivesの略で直訳すると目標による管理を意味します。具体的には「目標を通じて組織を管理する手法」であり、主に生産性の向上などを目的としています。
MBOとOKRの違いは何ですか?
生産性を高めるという目的は同じですが、人事評価に直結するかどうかなどが異なってきます。詳細に関しては記事内で解説していますので、ぜひ御覧ください。
おすすめ記事

