クリティカルシンキングとは?意味、メリット、ロジカルシンキングとの違いを紹介BLOG
2021.7.28
ビジネスの現場で「クリティカルシンキング」という言葉を聞いたことをある方も多いのではないでしょうか。多くの企業で注目されている思考法であり、ビジネスを推し進めていく上で欠かせないものとなっています。しかし、クリティカルシンキングという用語は知っていても「具体的にどんなものか分からない」「どう活用していいか分からない」という方も多いかと思います。
今回はクリティカルシンキングについて、メリットや実践の方法まで詳しく紹介していきます。
クリティカルシンキングとは?

クリティカルシンキングとは「批判的思考」と呼ばれるものであり、主観的視点に囚われすぎないように俯瞰して物事を判断する思考法のことを指します。クリティカルシンキングの手法はアメリカの教育界から始まったものであり、子どもにも客観的な判断を持って知識を習得できるように体系化されたものです。
昨今では、このクリティカルシンキングはビジネスシーンでよく使われています。物事に対して「なぜこうなのか」「本当に合っているのか」といった問いを投げかけることで、よりアイデアの精度を高めたり、実践的な意見に近づけていける手法です。
クリティカルシンキングの目的
クリティカルシンキングは、問いに対して最も適切な解を導き出すために活用されます。その問いとは、「情報」や「意見」、「外的な環境」などについて、客観的に検証するために用いるものです。クリティカルシンキングによってさまざまな観点から適正がどうかを判断することで、本質的な結論を得られたり、自分や相手が十分に納得した上で意思決定ができたりします。
クリティカルシンキングのメリット

クリティカルシンキングが重要な考え方ということを紹介しましたが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。クリティカルシンキングにはさまざまなメリットがありますが、今回は「物事の本質を見極められる」「矛盾や抜け漏れをなくす」「新たな発想が生まれる」という3つに分けて紹介していきます。
物事の本質を見極められる
クリティカルシンキングを実践することで、物事の本質を見極めることができるようになります。クリティカルシンキングでは、「なぜこうなっているのか」「これは正しいのか」と問いを投げかけて検証するため、主観的な感情を除いた第三者的な考えを持てるようになるからです。また、不要な情報を出来るだけ排除して、解答に必要で本質的に重要な情報だけに注目することもできるでしょう。
そうすることで、無駄な時間をかけずに本質に近い議論が可能になるはずです。そこで得られた解答は、関係者も納得度の高いものになるでしょう。
矛盾や抜け漏れをなくす
クリティカルシンキングでは、議論した内容や検討した意見に関して矛盾している点や抜け漏れを減らすことが可能です。批判的に疑問を投げかけることで、気づくことができなかった矛盾点に気づきやすくなります。そうして出てきた矛盾点をそれぞれ潰していけば、抜け漏れなく結論に辿り着くことができるでしょう。
また、このようにして検討した内容は、精度高く適正なものに近づいています。そのため、正しい根拠に基づいた結論に辿り着く可能性が高いです。
新たな発想が生まれる
クリティカルシンキングでは、さまざまな観点から疑問を投げかけることで新たな発想が生まれやすいです。最初は一つの考えしか浮かばなかった内容に関しても、批判的な疑問によって、全く新しい解決策やアイデアに繋がります。例えば、「営業成績をアップするには、新規開拓を増やすのが良い」という意見に対して、「既存顧客へのアプローチは適切か?」「他業務で効率化できる部分はないか?」と、別角度の疑問を投げかけるのです。そうすると、「他業務を効率化し、余裕ができた時間を既存の大口顧客へのアプローチ強化に使った方が良い」など、別のアイデアに繋げることができます。
新しく出たアイデアが最善のものとは限りませんが、さまざまな選択肢を比較することで、より適切な選択が可能になるでしょう。
クリティカルシンキングの基本的な考え方
クリティカルシンキングにはさまざまなメリットがあり、発揮する場面も多様です。ただクリティカルシンキングには、抑えておくべき基本的な考え方があります。ここでは「目的を常に意識する」「思考の癖があることを前提にする」「問い続ける」という3つの基本姿勢について、それぞれ紹介していきます。
目的を常に意識する
クリティカルシンキングでは、さまざまな角度から問いを投げかけて思考をしますが、どういう目的で思考するのかを意識することが重要です。
目的が明確になっていない状態でクリティカルシンキングをしても、意味のない内容を検討してしまったり、本質的な内容までたどり着けない可能性が高くなります。クリティカルシンキングにはある程度技術がありますが、そればかりに頼りすぎないように、常に目的を意識して思考するようにしましょう。
思考の癖があることを前提にする
クリティカルシンキングにおいて、思考することに関して人によって癖があることを理解しておく必要があります。他人だけでなく自分にももちろん思考の癖があり、それらは「価値観」「思い込み」などこれまでの経験や環境が要因となって形成されているものです。そのため主観的な思考には癖があることを前提にし、できる限り客観的な視点で思考することが重要になります。
問い続ける
クリティカルシンキングでは、常に思考し、問い続けることも重要です。思考の目的を明確にした上で、常に考え続けることで本質的な結論に近づいていきます。特にビジネスの世界においては変化が大きいため、問い続けた先に新たな課題が見つかることが多々あるでしょう。それを繰り返すことで、本質的に意義のある活動をしながらビジネスを推し進めていくことができます。そのため、例え結論にたどり着いたとしても、考えを止めることなく、「本当にそうか?」「なぜそうなのか?」と問い続けることがポイントです。
ロジカルシンキングとの違い
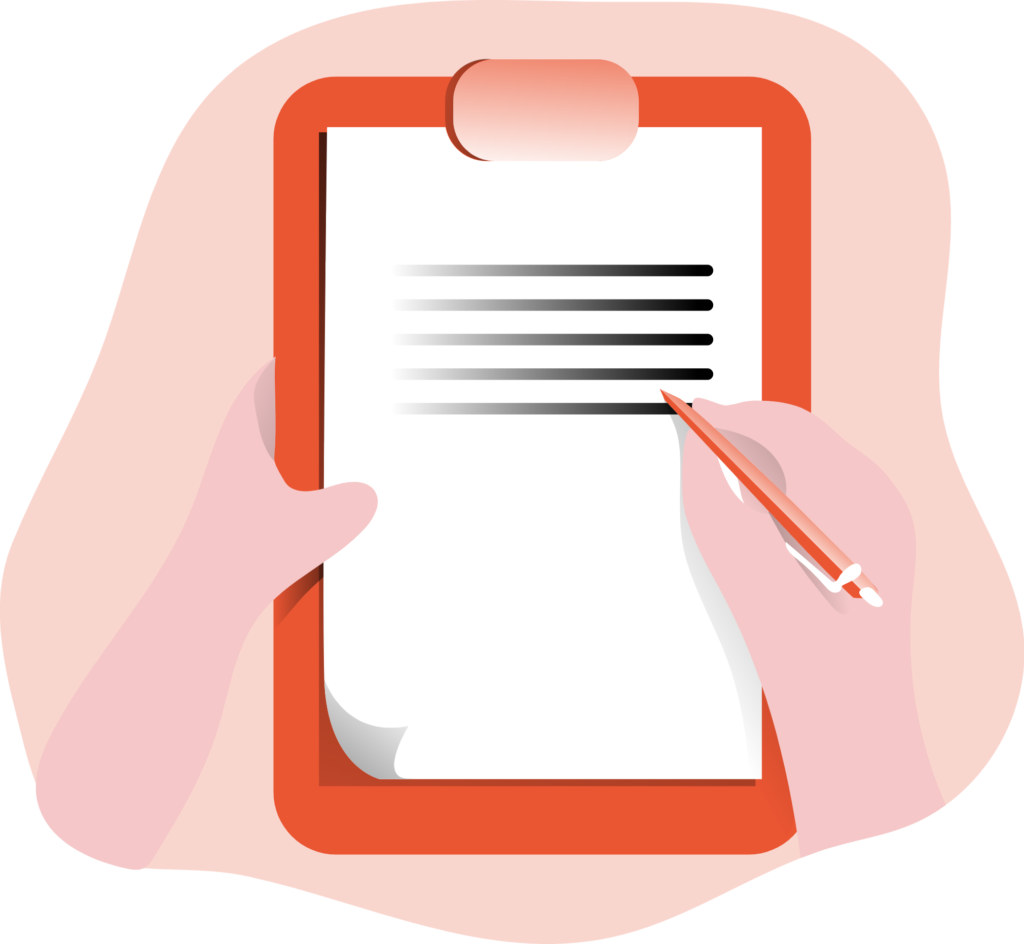
クリティカルシンキングと似たような用語で「ロジカルシンキング」があります。クリティカルシンキングが批判的思考であるのに対して、ロジカルシンキングは論理的思考という意味を持っており、こちらもビジネスシーンでは重要な考え方だと言えるでしょう。では、具体的にクリティカルシンキングとロジカルシンキングはどのような違いがあるのでしょうか。
ロジカルシンキングはある事象に対して、細かく分解して整理し、論理を組み立てて内容を検討する思考法です。一方でクリティカルシンキングは、前提条件に対して疑問を投げかけて検証する態度をとります。つまり、思考の出発点が双方真逆であると言えるのです。そのため、この2つの思考法に優劣はなく、2つを併用して活用することでより効果的に内容を検討することができます。
クリティカルシンキングの実践方法
ここまでクリティカルシンキングのメリットや基本的な考えを紹介してきましたが、具体的にはどのように実践すれば良いのでしょうか。
クリティカルシンキングの実践方法は「ゴールを明確にする」「現状を分析する」「課題を発見する」「解決のための行動を計画する」という4つのステップに分けることが分けることができるため、それぞれについて詳しく紹介していきます。
ゴールを明確にする
まずはクリティカルシンキングを活用する目的を明確にするために、「どんなことをしたいのか」「なぜしたいのか」を客観的に整理していきます。このステップでゴールを明確にしておくことで、クリティカルシンキングの精度が高まるのです。設定するゴールはできるだけ具体的になるよう、「達成基準」と「達成期限」も合わせて明確にしておくことが重要になります。
現状を分析する
ゴールが明確になったら現状の分析を行います。設定したゴールや達成基準、または達成期限に対して、現状はどうなっているのかを細かく分析しましょう。現状を正確に把握しておくことで、クリティカルシンキングがより効果的になります。現状を把握する際は、数値や具体的な指標で整理しておくとより次のステップが進めやすくなるので、意識すると良いでしょう。
課題を発見する
現状を分析できたら、整理した内容をもとに課題を発見します。設定したゴールと現状にどのくらい差分があるのか、その差分はどれくらいの大きさなのかを改めて分析し、何を解決すればゴールに近づけるか課題を明確にするのです。課題を設定する際は、定量的なデータをもとに差分の大きいものや重要度の高いものなどに優先順位をつけておくことが重要になります。課題はひとつだけではないことが多いため、優先順位を決めておくことで目的を見失わずにゴールに向かうことができるでしょう。
解決のための行動を計画する
最後に見つけた課題に対して、どのように目的を達成するのか行動計画を立てます。課題に対してつけた優先順位の高いものから「誰が」「何を」「いつまでに」「どのようにして」と具体的なアクションができるとこまで落とし込んで、計画を立てるのです。行動計画を立てる際は、すぐに動けるところまでアクションを具体的にしておくことが重要になります。そこまで具体的にしておかないと、結局やらずに終わってしまう可能性が高くなるでしょう。
クリティカルシンキングを実践して課題解決をしよう
クリティカルシンキングは、ビジネスシーンで課題解決の有効な手段として活用することができますが、日常生活でも意識して思考法を用いることで鍛えることが可能です。日ごろから前提条件を疑ったり、違う観点から問いを投げかける習慣をつけてみましょう。そうすることで、いざビジネスの現場で必要となった際も効果の高い結論に辿り着くことができるはずです。
こちらの記事を参考に、ぜひクリティカルシンキングを実践してみてください。
おすすめ記事
OKRを1つのツールに
まとめて運用しましょう
製品資料のダウンロードはこちら
お問い合わせ・導入のご相談はこちら
