ナレッジマネジメントとは?意味、メリット、導入ステップを紹介BLOG
2021.7.30
「ナレッジマネジメント」という用語を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか?ナレッジマネジメントとは、組織内で個々の社員が持っている知識やノウハウを共有し、活用することで企業全体の生産性を向上させていく手法のことを指します。競争や変化が激しい現代のビジネスシーンにおいて、組織全体で効率よく仕事を進めていくことは必須の働き方だと言えるでしょう。ただ、「ナレッジマネジメントが何か分からない」「実際に導入するにはどうすれば良いか分からない」といった人も多いかと思います。
今回はナレッジマネジメントについて、注目される背景からメリット、導入する際のポイントまで詳しく紹介していきます。
ナレッジマネジメントとは
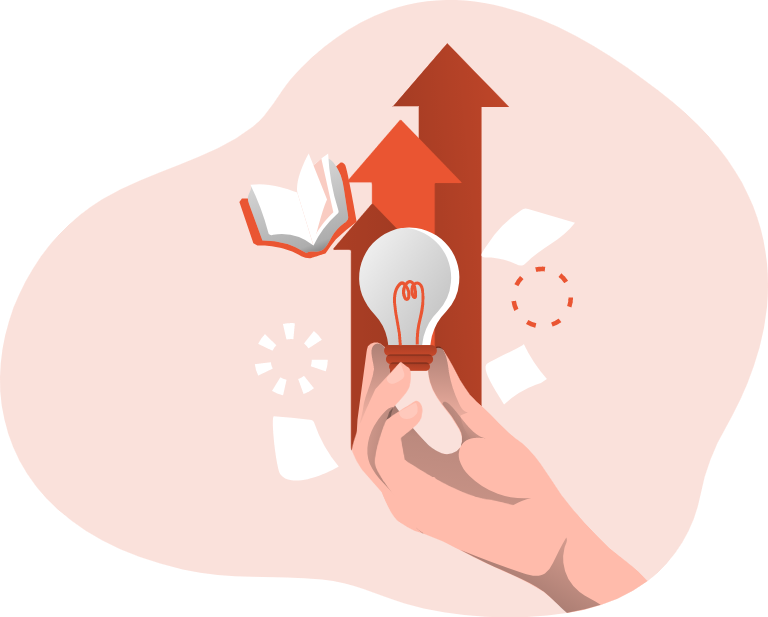
ナレッジマネジメントとは、企業組織や所属するメンバーが蓄積した知識やノウハウを組織内でシェアし、活用することで企業の生産性や競争力を高める手法のことを指します。
「ナレッジ(Knowledge)」は、知識や知見、顧客情報などの知的財産のことを示しており、これらを管理する行為としてナレッジマネジメントが活用されているのです。各メンバーが業務上で得た知見は個人の中、あるいは特定のチームの中だけで共有され、他の部門に横断的に共有されずに埋もれてしまうという場合が多くあります。他の部門でも活用することで生産性が向上したり、無駄を削減できる可能性のある知見が埋もれてしまうことは、組織全体にとっての損失になるため、ナレッジマネジメントによって簡易的にでも情報共有されることは企業活動を持続的に行う上で非常に重要です。
ナレッジマネジメントが注目される背景
ナレッジマネジメントは、経営学者であり一橋大学の名誉教授である野中郁次郎氏が提唱した「知識経営」がベースとなった手法です。伝統的な日本企業の強みとして、野中教授はベテランが持っている「暗黙知」が次世代に語り継がれることで技術や文化を根強いものにしていったことを挙げています。
では、なぜ自然に知識が継承される暗黙知とは相反するナレッジマネジメントが注目されているのでしょうか?
企業のあり方が変化してきている
知識が自然と継承されて、次世代に伝わっていく暗黙知が根付いていくには非常に長い時間がかかります。現代の日本企業では、伝統的な終身雇用制度が崩壊しつつあり、ビジネスを取り巻く環境も目まぐるしく変容しているため、時間のかかる知識継承の手法では企業として持続するだけの知識量を確保できなくなってきているのです。
企業の形式知を増やす
前述したようなビジネスシーンを取り巻く急速な変化に対応するべく、暗黙知をチームメンバーが活用できる形式知へと転換することが求められています。もちろん全ての伝統的な暗黙知が形式知へと転換できるわけではありませんが、現代では転換するためのさまざまな手法が確立されているため、幅広い範囲の暗黙知を形式知に変えて共有できるようになっているのです。そのおかげで、チームメンバーの生産性を向上させたり、従来は現場に行ってベテランに長期間つきながら継承する必要があった技術も短期間で習得できるようになったりと、さまざまな成果がみられるようになっています。
ナレッジマネジメントのメリット

実際にナレッジマネジメントを導入することでどのようなメリットがあるのでしょうか?組織によって、メリットに感じる部分はさまざまですが大きく分けて「業務効率化が進む」「最善策を横展開できる」「組織の競争力が向上する」という3つのポイントが挙げられます。
ここからは3つのメリットについて、それぞれ詳しく紹介していきます。
業務効率化が進む
各メンバーが業務の中で得た知見を蓄積し、それらを管理・分析することで業務を効率化させることができます。例えば、これまで紙媒体で管理していたデータをデジタル化することによって、作成する工数の削減やデータ閲覧スピードを向上することが可能になるでしょう。
営業活動や事務作業など、これまでそれぞれが自分のやり方で行っていた業務に関しても他のメンバーの手法を参考にしながら業務フローを見直したり、マニュアル化するなどして効率よく改善していくこともできます。業務のやり方がそれぞれのバラつきがなくなることで、より安定して組織としての成果が出せるようになるでしょう。
最善策を横展開できる
ナレッジマネジメントを導入して情報共有ができるようになることで、別部門や他店舗で効果があった施策を他の場所でも横展開できるようになります。情報共有の仕組みが整備されていないと、いくら組織にとって重要な知見であっても埋もれてしまい、他の場所で同様の課題が出てきた時に無駄な工数をかけてしまう可能性が高いです。ナレッジマネジメントによって知見が共有されることで、同様の課題に対しての最善策をすぐに実践することができ、効率よく改善を進めていくことができます。
組織の競争力が向上する
ナレッジマネジメントによって知見が共有できるようになることで、メンバーそれぞれの業務におけるパフォーマンスが向上し、組織としての競争力も向上します。メンバーが営業データやノウハウ、マニュアルや技術開発の最新情報など、業務に関するさまざまなデータにスムーズにアクセスすることができ、必要な時に必要な情報を手にできるため、主体的に業務を進めていくことができます。また、部門を超えた情報共有もされているため、横断的なプロジェクトを進めやすくなるのもメリットです。
ナレッジマネジメント導入のステップ

ナレッジマネジメントにはさまざまなメリットがありますが、実際にどのように運用して行けば良いのでしょうか。組織によってどんなナレッジマネジメントを導入して運用すれば良いかは異なりますが、大きく分けて4つのステップで導入を検討するのが良いです。
ここからはナレッジマネジメントを導入するために必要な4つのステップについて、それぞれ詳しく紹介していきます。
導入目的を明確にする
まずはナレッジマネジメントを導入することで、どのような課題を解決したいのかを明確にすることが重要です。「情報共有をスムーズに行いたい」という抽象的な目的では、ナレッジマネジメントの構築はうまくいかず、あまり効果を発揮しないでしょう。例えば、「新規顧客を前年度より○件増やし、売上高を○○%向上させたい。そのために情報共有をして、営業効率をあげたい」というような目的があれば、それに見合った営業効率化に向けたナレッジマネジメントを導入・構築することができます。
どの情報を共有するか決める
目的が定まれば、具体的にどんな情報を共有すればその目的を達成できるのかを検討していきます。企業の中には膨大な種類のデータが存在しているため、全ての情報を対象にナレッジマネジメントを進めるのはかなりの時間がかかってしまいます。その労力に見合った効果が得られるかを想定し、情報によって共有を進める優先順位をつけることがポイントです。最大の目的が「営業の効率化」であるならば、顧客データや営業活動のデータを優先的に共有できる仕組みを構築していくのが良いでしょう。
業務プロセスに組み込む
どんな情報を共有するか決まれば、具体的な業務プロセスのどこにナレッジマネジメントの仕組みを落とし込むのかを検討します。いきなり全ての情報を移行しようとすると、現場のメンバーの負担が大きくなってしまうため、段階的にナレッジマネジメントの仕組みに移行していくのが良いでしょう。例えば、個人で管理していた営業情報の一部をまずはナレッジマネジメントのシステムに入力して、徐々にそのデータ数を増やしていきます。
定期的に見直す
ナレッジマネジメントの仕組みは、データを移行すればそれで大丈夫というわけではありません。活用を進めていく中で、当初の目的と想定していた効果からズレが生じる可能性もあります。導入検討時には必要だと思っていたデータがあまり活用されてなかったり、実はこのデータを共有した方が効率が良くなるなど、運用していく中で新しい気づきを得ることができるのです。
そのようなフィードバックを受けて定期的に見直していくことが、ナレッジマネジメントで高い効果を生むためには重要です。
ナレッジマネジメントを導入する際のポイント
最後に、ナレッジマネジメントを導入する際に注意しておきたいポイントを、いくつか紹介していきます。

数値で効果を測りにくい
ナレッジマネジメントを導入するには、ある程度のコストがかかりますが、導入後の効果測定が数値でしづらいということに注意する必要があります。営業部門では、営業効率がアップすることで新規顧客数や受注件数など数値で評価することも可能ですが、それ以外の部門では事前に観測項目を決めておき、クレーム数・労働時間等の指標で評価できるように準備しておくのが良いでしょう。
ナレッジ共有を快く思わない人もいる
ナレッジマネジメントは多くのメリットがありますが、独自で編み出したり得た知見を他の人に簡単に渡したくないと感じる人も少なからず組織内には存在するでしょう。そういった方の理解を得ずに導入を進めてしまうと、後からトラブルに発展する可能性もあるため、事前に導入する目的や意義、価値の高いノウハウを持っている人への対価などを伝え、納得を得ることも大事なポイントです。
ナレッジマネジメントを導入して生産性を上げよう
働き方が多様化している現代社会では、外部環境の変化が早くなっており、チーム内でのノウハウの継承も従来の方法では追いつかなくなっています。ナレッジマネジメントの仕組みを導入するなどして、積極的に価値の高いノウハウを共有し、企業全体の生産性向上に繋がるようにしましょう。
おすすめ記事
OKRを1つのツールに
まとめて運用しましょう
製品資料のダウンロードはこちら
お問い合わせ・導入のご相談はこちら
