コアコンピタンスとは?意味、ケイパビリティとの違いを紹介
更新日: 2021年7月31日
競争の激しいビジネスシーンの中で、「コアコンピタンス」という考え方が注目されています。コアコンピタンスとは、企業が持つ能力の中でも他社にはない自社独自の能力のことを指し、これによって競合企業との差別化を図りながらビジネスを成長させていくことができるものです。ただ、コアコンピタンスという用語は知っているが「意味を正しく把握していない」「どのように自社のコアコンピタンスを見つければいいか分からない」という方も多いかと思います。
今回はコアコンピタンスに関して、意味や条件、自社のものを見極める手順などさまざまな観点で詳しく紹介していきます。
コアコンピタンスとは

コアコンピタンスとは英語の「Core competence」を語源としており、企業のコアとなるビジネスにおける独自の強みや能力のことを指します。経営学者のゲイリー・ハメル氏などによってもともとは提唱されており、単に自社が得意としていることや製品のことを指すのではなく、競合が真似できないような圧倒的な差別化ができる能力のことをコアコンピタンスとして位置付けています。そのため、自社のコアコンピタンスを把握したり確立したりすることは、現代の変化が激しいビジネスシーンにおいて企業活動を持続的にしていくに当たって、必要不可欠であると言えるでしょう。組織を牽引するリーダーは、特に自社のコアコンピタンスを正しく把握しておくことが重要です。
コアコンピタンスの条件

組織におけるコアコンピタンスには、どのようなものが当てはまるのでしょうか。コアコンピタンスに該当するものには、3つの条件があると言われています。どの条件が欠けていても、コアコンピタンスとは言えないため、正しく把握しておきましょう。
ここからは3つの条件について、それぞれ詳しく紹介していきます。
顧客に利益があること
コアコンピタンスとして認められる能力には、関係する顧客にとって利益があることが条件として挙げられます。いくら他社とは違った特有の能力であり組織にとって大きな利益をもたらすものであるとしても、顧客にとって不利益なものはコアコンピタンスとしては認められません。顧客が満足のいっていないことで利益を出している手法では、一時的に利益をあげることはできるかもしれませんが、長期的な目線でみて、企業としての圧倒的な強みを発揮することは難しいと言えるからです。
競合他社に模倣されないこと
コアコンピタンスとは他社にはない自社の圧倒的な強みのことを指すため、他社に真似されないというのもコアコンピタンスの条件として挙げられます。仕組みが容易だったり、再現性の高い強みだと他社でも同様のことが実践しやすいため、最初のうちは優位を保てていたとしても、長期的には優位性を維持することが難しいです。他社で真似できないような能力を自社で持つことができれば、顧客が離れることを防ぐことができ、継続的な企業活動を実現できます。
幅広く応用できること
ひとつ商品に関しての能力ではなく、ほかの商品に関しても応用が効くこともコアコンピタンスの条件になります。特定の商品にしか効果を発揮しない能力では、その商品のニーズが少なくなってきた場合に企業としての強みと言えなくなってきてしまうのです。常にニーズが一定の商品はないといっても過言ではないため、さまざまな商品に対して幅広く応用が可能な能力を確立しておくことで、時代の変化に左右されにくい組織になるでしょう。
コアコンピタンスとケイパビリティの違い
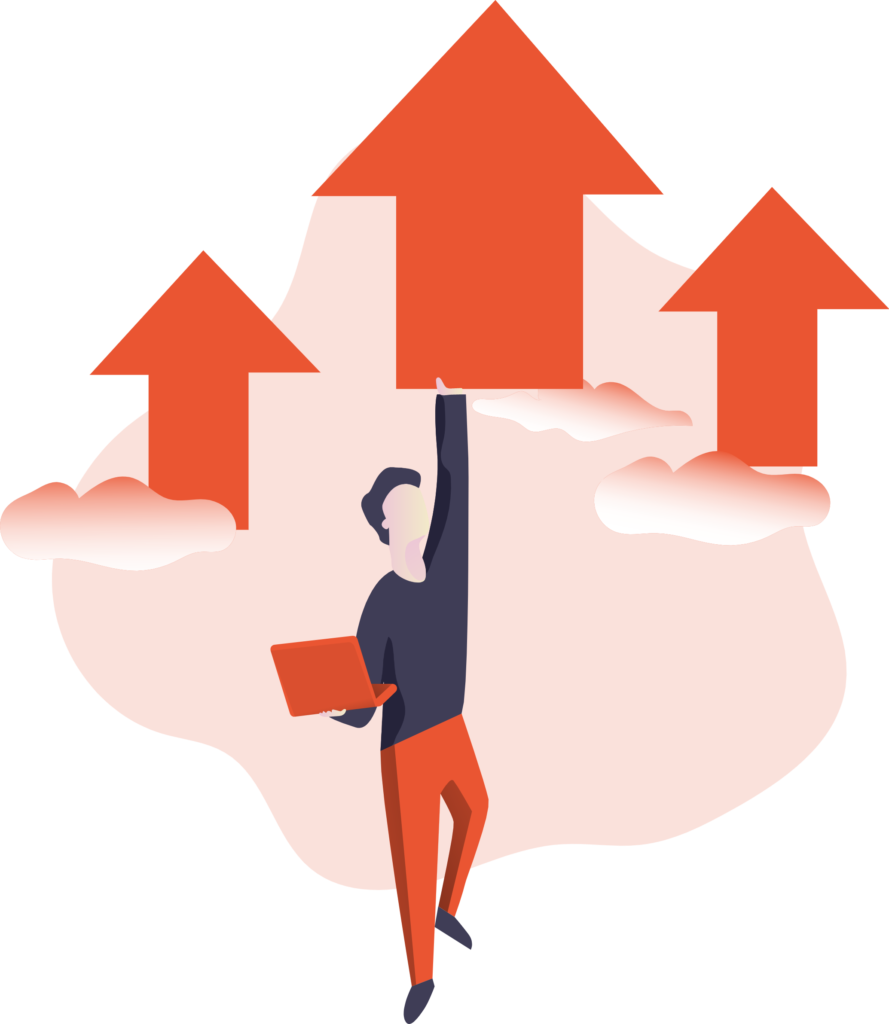
コアコンピタンスと同じように企業の能力を表す言葉として、「ケイパビリティ」があります。コアコンピタンスとケイパビリティは、共に企業が持つ圧倒的な強みのことを指しますが、意味としては明確な違いがあります。コアコンピタンスが他社が真似できないような差別化ができている特定の強みのことを指しているのに対し、ケイパビリティは組織を横断的にみた時の圧倒的な強みのことを指すのです。ケイパビリティは、より企業戦略に近い性質を持っています。ただ、意味としての違いはあるものの相反するものではなく、むしろ相互に補い合っているものだとも言えるのです。ケイパビリティが確立されていることによって、コアコンピタンスを強める投資が行えるようになり、さらにケイパビリティが強まる、とった関係性にあります。
コアコンピタンスを見極める手順

では、実際にどのようにして自社のコアコンピタンスを見極めていけば良いのでしょうか。コアコンピタンスを見極めるには主に「強みの抽出」「強みの判定」「強みの評価」という3つの手順が存在しています。
ここからはそれぞれの手順について、詳しく紹介していきます。
強みの抽出
まずは、自社にはどんな強みがあるのか、人材や文化、商品などから思いつく限りリストアップしていきます。現時点で有している強みはもちろんのこと、手に入れることが想定される能力や商品に関してもその対象に入るでしょう。この段階においては、さまざまな視点からコアコンピタンスになり得る強みを探し出しておきたいので、リーダー層だけでなく現場の社員や関係する取引先などの意見もヒアリングし、多角的に強みを抽出するのが良いです。
強みの判定
次に抽出した強みの中で、前述したコアコンピタンスの条件である「顧客に利益がある」「競合他社に模倣されないこと」「幅広く応用できること」「幅広く応用できること」の3つに当てはまるかどうかの判定を行います。この中のひとつでも当てはまらないものがあれば、それはコアコンピタンスとしては認められないため、慎重に検討する必要があります。この判定も、リーダー層だけの判断では偏る可能性があるため、必要に応じて現場のメンバーも交えて検討の場を設けても良いでしょう。
強みの評価
最後に3つ条件に当てはまると判定した強みに関して、コアコンピタンスとしてふさわしいかどうかをさらに評価します。ここでの評価の基準は、コアコンピタンスとして競合他社に比べてどのくらい優位性があるかという点です。評価方法としては、「模倣可能性」「移動可能性」「代替可能性」「希少性」「耐久性」という5つの要素で実施します。
ここからはそれぞれの評価要素が、どのようなものなのか詳しく紹介していきます。
模倣可能性
強みとなる能力や商品、技術力などが競合他社に真似できるものがどうかを評価します。容易に模倣ができるような強みであっては、他社の優位にたつ圧倒的な強みにはなり得ないでしょう。例え、現時点ではたくさんの顧客に求められているような商品でも、資本力のある他の競合他社に真似されてしまえば、すぐに商品価値が下がって優位を保てなくなってしまいます。抽出して判定した強みが、なぜ、どの程度真似されないのかも合わせて考えて見ると良いでしょう。
移動可能性
特定の商品やサービスだけでなく、他の商品にも転用や活用ができるものなのかという、いわゆる汎用性を評価します。汎用性がないものを強みにしてしまうと、それに紐づく特定の商品やサービスのニーズが落ちてしまった際に優位性を保てなくなってしまいます。汎用性の高い強みを持っていると、他の商品を開発する際やサービスを展開する際にも、強みを活かして事業展開をしていくことができるため、企業力を底上げすることができます。そのため、他社が同様の商品を作ったりしても、常に新たな可能性を広げていくことができるのです。
代替可能性
自社の強みとなる能力や商品が、競合他社の商品やサービスにとって代わるものかどうかを評価します。競合他社が持っている強みを活かしても取って替えることができず、常に優位性を保っていられるものが価値の高い強みになります。そのような強みを持っておくことで、顧客から高い評価を得ることができ継続的な取引に繋がるでしょう。それによって、企業としての価値も高くなり、さらに幅広い顧客に対して独自の強みを持った価値を提供できるという、いい循環を作り出しすことができます。
希少性
これまでにないような技術、珍しい素材を使った商品など、強みが希少性を有しているかを評価します。希少性が低い強みだと、いくらいい価値を生み出したとしても目につかず、顧客に届くに至らないという可能性が高いです。さらに希少性が低いと、他社に真似されやすいため、圧倒的な優位を保ことができないでしょう。希少性が高い強みを確立することで、顧客の目に届きやすくなり、他社が参入できない場所でビジネスを展開していくことが可能になります。
耐久性
最後に、強みが時代の変化や流行り廃りに左右されずに、普遍的に人々に必要とされるものかどうかを評価します。変化に弱い耐久性が低い強みは、例え一時的に注目を浴びて他社よりも優位に立ったとしても、価値を持続させることができずに、飽きられたり他に特異な物が現れた時に一気に需要が低下してしまうでしょう。特に現代のビジネスシーンではグローバル化やIT化が推し進められている影響で、以前に比べて変化が激しい時代になっています。そんな中で耐久性のある新しい商品やサービスを作り出すことは容易ではありませんが、確立することができればコアコンピタンスとして企業を支えてくれるものになるはずです。
コアコンピタンスを見極めて効果的な企業活動を
コアコンピタンスは単なる強みではなく、他社の優位にたつ圧倒的なものでなければなりません。そのため一長一短で確立できるものではありませんが、自社の強みを正確に把握して伸ばしていくことで企業の核になっていきます。自社のコアコンピタンスを見極めて、効果的に企業活動に取り入れていきましょう。
是非今回の記事を参考に、組織一丸となって自社のコアコンピタンスを見つけてみてください。
おすすめの記事
LOADING...
OKRをカンタンに導入できる
クラウドツールを試してみませんか?
\ 商談不要!メールアドレスだけですぐに開始 /
