OKRは社員が成長するフレームワーク!MBOとの違いや注意点を解説BLOG
2024.2.29
この記事ではOKRという目標管理のフレームワークについて、概要やMBOとの違い、運用時の注意点をご紹介します。
OKRは社員が成長するフレームワーク
OKRはObjective & Key Results の略称で、大きな目標に向かってチャレンジすることで、チーム一人ひとりの能力を加速度的に成長させるフレームワークです。高い目標に対し経営陣も従業員も一丸となって取り組み、変化を恐れないチャレンジングな企業文化を醸成します。
OKRでは最初に大きく企業全体のOKRを設定し、その後、チームや個人のOKRが作られていきます。
企業全体から個人まで目標の方向性が一致し達成プランが可視化されるので、社内のコミュニケーションが促進され、協力して目標達成を目指すことが可能です。
OKRは、もともとIntelが生み出し、その後初期のGoogleが取り入れて発展してきました。
近年ではシリコンバレーを始め海外の成長企業で活発に採用され、日本企業でも導入され始めています。
OKRについて詳しくは「OKRがマネジメントに良い理由とは?」をご覧ください。
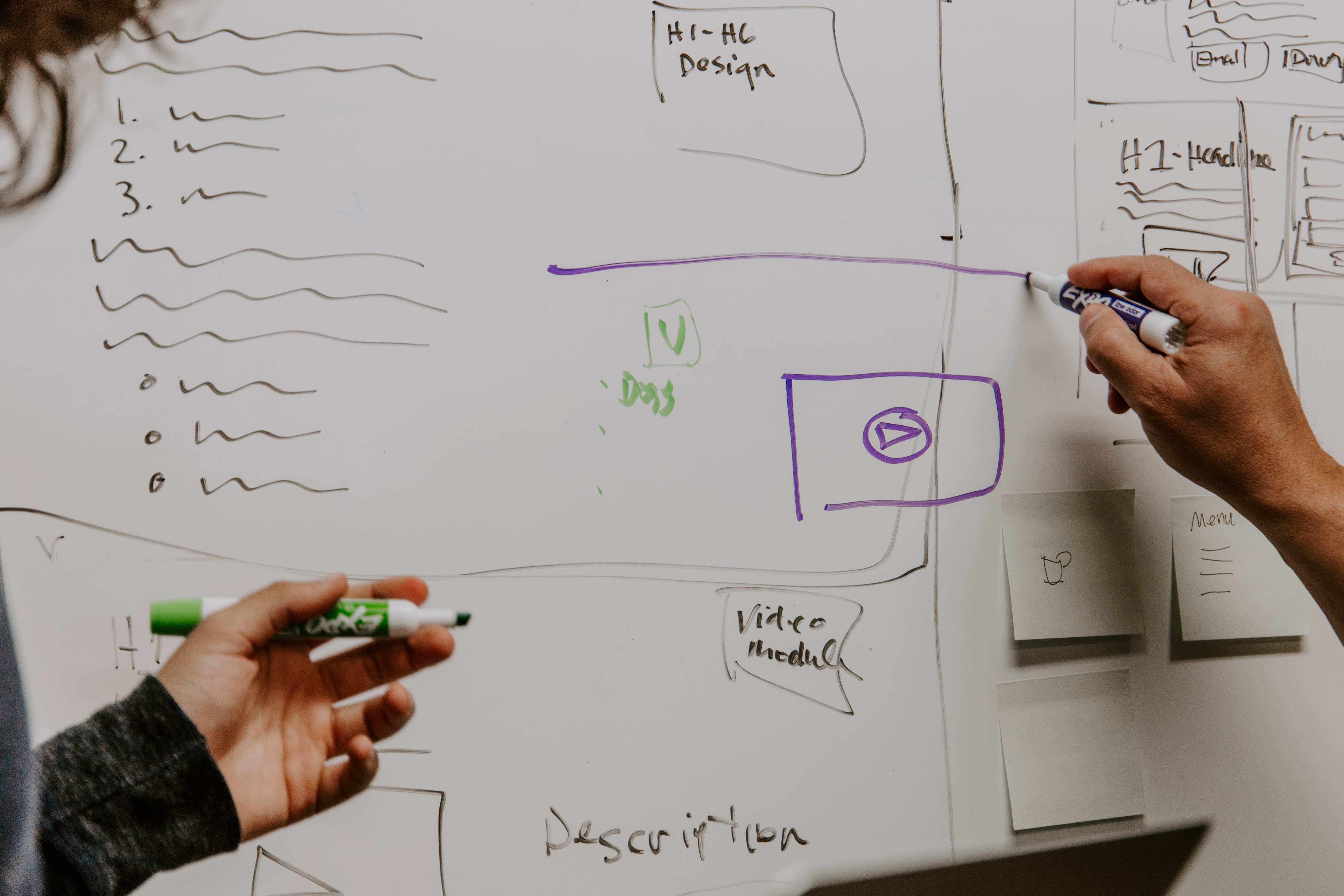
OKRと他のフレームワークの違いを解説
OKRと他のフレームワークは以下のように異なります。
MBOの目標はクローズに扱われるがOKRはオープン
MBOはManagement By Objective and self controlの略称です。日本語では、目標管理制度と訳されます。
MBOとOKRの違いは下記の通りです。
| ポイント | MBO | OKR |
|---|---|---|
| 導入目的 | 人事評価の材料 企業を維持したい | コミュニケーションの材料 大きなビジョンを実現したい |
| 目標の共有範囲 | 社員とその上司のみで目標を共有 | 社内全員が目標を共有 |
| 目標達成の測定基準 | 企業により異なる(「明確で具体的な目標」「達成可能な目標レベル」等が良く使われている) | SMARTの法則を用い客観的に測定できる |
| 評価サイクル | 半年に1回 | 四半期に1回 |
| レビュー頻度 | 半年に1回 | 毎週 |
| 達成基準 | 100%前後 | 60〜70%達成できていれば成功 |
報酬の決定に使われるMBOは、100%前後の達成度合いを求められる上に、目標はクローズに扱われます。
対して、業務の効率化やコミュニケーションを促す目的で使われるOKRは、60〜70%の達成度合いでも成功と考えられ、目標そのものも社内全員にオープンです。
OKRは、報酬の決定とはわけて使われるので、野心的な目標に挑戦しやすくなり、社員や企業全体が飛躍する助けとなります。
MBOについて詳しくは「目標管理(MBO)とは?メリットやデメリット、流れを紹介します。」をご覧ください。
KPI・KGIは部門ごとの目標設定に向き、OKRは会社全体の目標設定に向く
KPIとは、Key Performance Indicatorの略、KGIとはKey Goal Indicatorの略です。
KGIは企業全体の戦略的な目標設定であり、そこから落とし込んで業務の各プロセスにおけるKPIを設定します。
一見似ているように思えますが、KGIは目標を100%達成することを目指しており、その達成率を1%でも引き上げるためにKPIを活用します。
部門ごとに確実に達成したい目標を定め今ある業務を効率化するには、KPIやKGIを活かすことがおすすめです。
OKRは、企業全体が現状を突破してさらに飛躍するための目標を設定することに向いています。
KPI・KGIについて詳しくは「会社におけるKGIとは?KPIやOKRとの違いを解説します!」をご覧ください。

OKRを採用している代表的な企業
OKRを採用している企業は数多いです。代表的な企業を2つご紹介します。
Googleは、社員がまだ40名だった初期からOKRを取り入れ、現在でも活用し続けています。
2000 年代初めに、創業時からGoogleに出資している投資家のジョン・ドーア氏によって、OKRが導入されました。
Googleは、OKRを企業戦略の設定に利用し、四半期ごとに数回見直して活用しています。
また、「ストレッチゴール」と呼ばれる、社員自身が達成可能と考える設定値よりさらに高い目標を設定する手法も組み合わせて利用しており、継続的な企業発展に活かしているのです。
株式会社メルカリ
フリマアプリ「メルカリ」を手がけている株式会社メルカリも、初期からOKRを導入しています。
株式会社メルカリでは、OKRとMBOを併用し、成果を評価とも結びつけている点が特徴です。
3ヶ月に1回上司が社員と面談を行い、こまめなOKRの見直しやコミュニケーションの活性化をはかっています。

OKRは目標を可視化することでコミュニケーションを促進する
OKRは目標管理・達成ツールとしてだけではなく、コミュニケーションツールとしても優秀です。
同じ会社で働いていても、他者がどのような仕事をしているのかよく知らないということは珍しくありません。
しかし、OKRで企業全体の方向性が明確化され目標が可視化されていると、透明性が増し社員同士のコミュニケーションがはかりやすくなります。
部署やチーム全体で協力関係を築きやすくなり、また他部署や他のチームと一緒に活動して目標達成を目指すことも可能です。
OKRを導入することで企業内の風通りがよくなり、企業全体の一体感が高まる効果を期待できます。
(参考の導入事例:株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社「OKRでチームの関係性、思考、行動が変化した」)OKRは定期的に更新することを前提で運用する
野心的な目標を設定し達成のために行動する中で、予期せぬ事態に遭遇することもあります。なぜなら今までの範囲を越えて成長を目指すからです。
そのため、OKRはは定期的に見直しをして更新することを前提として運用されます。
目安としては四半期に1回。まだOKRに慣れていなければ1ヶ月に1回は見直しをしましょう。
目標達成に向けた最適なアクションを探り行動していくことが大切です。
また頻繁にOKRを見直すことで、社内のコミュニケーション活性化にも役立ちます。

OKR運用の注意点!報酬制度とは切り離す
OKRでは高い目標の達成を目指すために、達成率は60〜70%で成功と考えられています。報酬制度とも切り離すことが基本です。
OKRの達成率が報酬制度と結びついてしまうと、報酬を落としたくないために100%達成することが可能なレベルの低い目標を設定してしまう恐れがあります。
OKRを運用する際は、報酬制度とは切り離し、社員がよりレベルの高い目標にチャレンジできる体制を整えることが肝心です。
なお、報酬制度にも成果を活かしたい時は、MBOと組み合わせるなど、他のフレームワークと併用する方法をおすすめします。
OKRを活用して自社の飛躍的な発展を目指そう!
OKRを導入することで、個人ひいては企業全体が、現状の水準を越えた飛躍的な発展を目指すことができます。
Googleは、当初社員が40人だった頃からOKRを導入し、現在では120,000人を越える世界的な大企業に成長しました。
変化の激しい現代において、継続的に発展を遂げるためには、野心的な目標へのチャレンジが欠かせません。
おすすめ記事
