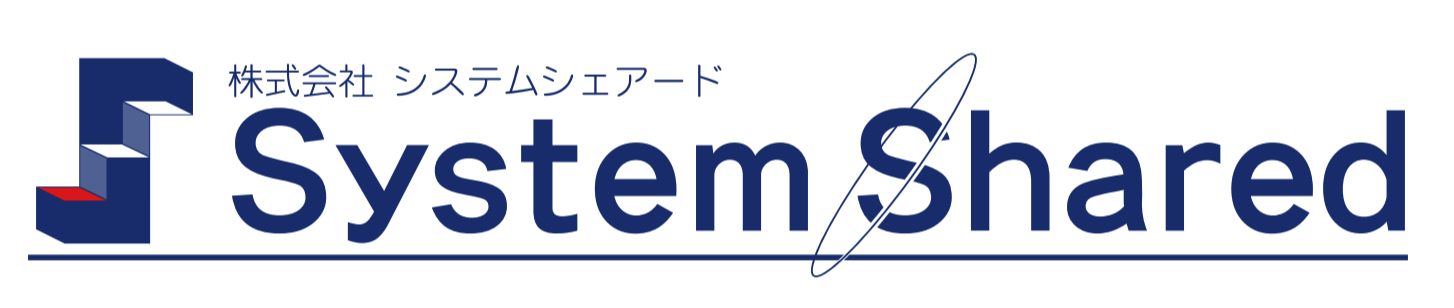株式会社システムシェアードは開発事業と教育事業を主軸に展開するIT教育のエキスパート。
2007年に創立してから毎年平均140%の増収を続けており、経産省や千葉県、松戸市からも表彰されている注目の企業です。
そんなシステムシェアードが新たなフェーズへ移行する足がかりとして、この度OKRツール「Resily(リシリー)」を選定いただきました。
インタビューに応じていただくのは、経営企画室の部長を務める須賀 祐介様。須賀様にはOKR導入に至った経緯やハードル、導入効果や今後の展望まで、幅広くお話をうかがいました。
<聞き手/Resily 取締役 西川>
―早速ですが、システムシェアード様の事業内容について教えていただけますか
はい。弊社は主に開発事業と教育事業の二つの柱を持っています。
開発事業はスマートデバイス向けアプリケーションや昔ながらのWEBアプリケーションに関する業務システム構築が多く、教育事業に関しては新人向けのJava研修を主に実施しています。2年前からは「7つの習慣」をプログラムに盛り込んだ研修も始まりました。
この教育事業については特に伸びていまして、2年前に某大手調査会社で調査してもらったときは、BtoBにおける新人向けJAVA研修受講者数で都内1位を獲得しています。
―すごいですね。ちなみに須賀様の役回りはどのようなものなのでしょうか
私は、昨年立ち上がった経営企画室の部長を務めています。
業務内容としては組織改革と新規事業の立ち上げ、後はコミュニケーションラインの整理などになるかと思います。
新しく立ち上がった組織のミッション、それは会社の限界を引き上げること
―なるほど。新しく立ち上がったという経営企画室のミッションを教えてください
代表からは「会社の限界を引き上げること」を指示されています。
―会社の限界。
はい。弊社には以前「開発部門」というところがありまして、ここが1番古くからある部門で在籍者数も多く、同時に課題が多い部門でもありました。
この部門を既存顧客と新規開拓の2つに分けることで現場の課題感と会社の課題感のズレを解消しようというのが、最初に手をつけた取り組みです。

目標設定を改革しようと導入したBSC(バランストスコアカード)は浸透せず失敗
―なるほど。部門を2つに分けて実施したことは何ですか
まず実施したのが、組織の目標設定に対する認識を改めることです。
社員一人ひとりがそれぞれボトムアップで目標を決めるやり方はいい部分もありますが、組織が大きくなるにしたがって徐々に統率が取れなくなってきました。これを解決するために、より効果を発揮できる方法を確立しなければなりません。
実はOKRの前にBSC(バランストスコアカード)の導入を進めていたのですが、それは残念ながら失敗してしまいました。
補足:BSC(バランストスコアカード)
企業の戦略やビジョンを4つの視点「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」の視点で分類し、可視化する業績評価システム
―BSCがうまくいかなかった理由は何だったと思いますか
そもそも我々の目標管理に対するリテラシーが低かった、ということが挙げられます。
これまでと違うやり方に対して、アレルギー的な反応が出てしまいました。
BSCは評価の視点が明確で論理的な点が特徴ですが、スピードや柔軟性を強みにしていた弊社にとってはそれが足かせとなってしまいました。
そこで、欧米のIT企業や日本でも伸びている企業が導入しているOKRを検討したのです。
―OKRを知ったきっかけを教えてください
Resilyを導入している企業に勤めている方が社内でセミナーを開いてくれたことがきっかけです。その中でたまたまOKRについての話があり興味を持ちました。
その後、自分でもOKRについて勉強しようと調べてみたのですが、国内ではまだ情報が少なくわからない部分が多い。そこで実績のあるResilyさんに導入をサポートしてもらうことにしたのです。
覚悟を持ってOKR導入を提案、代表からは「1度決めたことはやり切れ」と後押しをもらう
―OKRを導入する際のハードルはありましたか
やはりBSCの件があったので、「本当に効果はあるのか」「最終的な結果(業績)につながるのか」という声は多く出ましたね。そんな中でOKR導入を提案するには、ある程度の覚悟が必要でした。
―OKR導入がうまくいったのは、どんなところがポイントでしたか
まずはResilyさんに一緒に入ってもらって、目標管理に対するリテラシーを高めることができた点が大きかったと思います。このおかげで、社内での会話のキャッチボールが成立するようになりました。
あとは弊社の代表から明確なゴーサインをもらっていた点ですね。
代表も目標管理に対しては同じ課題感を持っていたため話が早かったです。加えて代表のスタンスは「1度決めたことはやり切れ」。その後押しもあってブレずに進めることができました。
OKRを使うことで「生産性の大きさ」が見える化され、物事を「経営課題の大きさ」ベースで話せるようになった

―OKRを運用する中で課題は出ませんでしたか
そうですね……うーん、正直あまり見当たらないんですよね(笑)
これはメリットとも言えるかもしれませんが、強いてあげるのであれば、生産性の低いものがシビアに浮き出てくる点でしょうか。
これまでは思いつく施策を、それこそ20個も30個も優先順位をつけずにやっていました。一方、OKRでは「そもそもこの施策はいらないのでは?」ということに気付かされます。これは、その施策に関わる当事者にとってはなかなか辛いことかもしれません。
でも、そのおかげで生産性の低いものが表層化する。物事を経営課題の大きさベースで捉え、パフォーマンスのレベルがグッと底上げされた感覚があります。
―その他に「もっとこうしておけば良かった」みたいなことはありませんか
OKRを導入するときはトップ層を巻き込み、時間をかけずに一気に導入した方が良いと思います。時間をかけ過ぎると、その過程で迷いが生じる可能性があるためです。
あと、最初からResilyさんのOKRツールは導入すべきでした。最初は導入に反対していたり、「スプレッドシートで十分なのではないか?」と言っていた人も、ツールを触ったあとで意見が変わるというケースがあったからです。それほど、OKRツールは理解の濃さを変えてくれるパワーを持っていると思います。
OKR導入後の経営合宿で大きな変化。これまでは線だったつながりが、立体的な面に見えた
―OKRの導入効果はいかがですか?
弊社では毎年期末にマネージャーを集めて、来期に向けた経営合宿を開いているのですが、OKRの効果を大きく感じたのはその時です。
コミュニケーションの質が明らかに何段階も上がっていました。
これまでは意見を聞くと「バラバラの方向に向かっているな」と感じることが多かったのですが、今回はみんな最初から同じ方向を向いていました。
「会社がこういう成果を目指しているから、自分たちの部署はこういう方向を目指す」
こんな姿勢で全員が話し合いに参加していたのです。本当にその状況が信じられなくて、合宿の間ずっと鳥肌が立っていました。
この合宿は代表にも褒めてもらいまして、「これまでは線だったつながりが、立体的な面に見えた」と。そして「土台となる役割をOKRが担っていた」とも言ってくれました。
―それは我々にとっても最高の褒め言葉ですね。ありがとうございます!
あと、現在は個々が抱えているKey Results(具体的な数値目標)に対して週次で報告・共有してもらっていて、それによって「このObjective(組織の目標)がダメなら、他の戦略から考えないとね」といった価値ある会話が増えました。
システムシェアードの今後の展望「日本のITレベルの更なる引き上げを目指したい」
―システムシェアード様の今後の展望について教えてください
システムシェアードがこれまで培ってきた開発とIT教育をベースに、日本のITレベルの更なる引き上げを目指したいと考えています。
また、弊社の教育事業は研修が中心ですが、突き詰めていくとコーチングや目標管理なども教育に含まれてきます。今はエンジニア向けの研修ですが、そこから広げてマネジメント層や経営層なども貢献できることはまだまだ多いと考えてます。その中でOKRのフレームを取り入れるのも面白いかもしれません。
組織全体のパフォーマンスが高まれば日本のITレベルも引き上がりますし、弊社のビジョンである「人×ITで豊かな未来を創造する」に1歩近づくんじゃないかと。だからこそITスキルだけじゃなく、実際に成果が出せるフェーズまで関わっていけたらと考えています。
正直、このような方向性は、まだObjective(組織の目標)に入っていません。でも、OKRは途中からでも戦略変更できる柔軟性がある。その特性を活かして、その時その時にもっとも優先すべき課題に集中して取り組んでいきたいですね。
※本記事は2019年4月時点のものです。