全社にOKRを浸透させるためのキーは「遊び心」自分たち流のOKRを形づくる導入事例
クリエーションライン株式会社
クリエーションライン株式会社様(以下:クリエーションライン)は「IT技術によるイノベーションにより顧客と共に社会の進化を実現すること」をビジョンに、クラウド、OSS、アジャイル、DevOps、データ解析・機械学習等の先端技術について多くの経験および知識を有するITプロフェッショナル企業です。
2019年6月にResilyの導入・運用を開始したマネージャー荒井裕貴氏に、OKRやResily導入の背景や決め手、今後の取り組みなどについて伺いました。
お話を聞いた方
マネージャー 荒井 裕貴氏

変化の激しい会社ではMBOは機能せず
Resily:
OKR導入以前に人事評価制度のようなものを取り入れていたのでしょうか?
クリエーションライン株式会社 マネージャー 荒井 裕貴氏(以下、荒井):
そうですね、年間でいわゆるMBO(※1)に近しいような取り組みとそれに連動した評価を行っていました。
期初に目標を設定して期末に目標に対する取り組み状況、自己評価をして上長に提出するといった形ですね。
この取り組みの中の問題点を言うと、期初に目標を設定して期末に評価する形になるので、期中はその存在すら忘れているという現実がありました。
評価という行為を達成するためのプロセスになっていた、いわゆる「やらされ」の状態でしたね。
1年間というサイクルだと、期初に設定したことが、期中には状況やロールすらも変化することがあったので、期末でその目標はとっくに自分のミッションでなくなっているといったこともあったんですよ。
3ヶ月ごとに違うプロジェクトにアサインされる人もいるような変化の多い会社だったので、そういう人からすると余計に1年間の目標は当たり障りのない目標になってしまうといった問題もありました。
(※1:Management by Objectives、目標を達成するためのステップとして、具体的にどんなタスクにどれほどの時間を使い、どのような成果を出したのかを従業員自らが可視化・把握する一連のフレームワークのこと。)
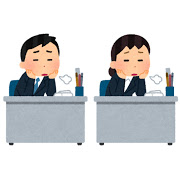
Resily:
そのようなこともあって検討した結果、OKRを導入することになったと思うのですが、どういうきっかけで導入に至ったのですか?
荒井:
書籍がリリースされたことで、世の中にOKRという言葉が出回ったことが一つの要因ではあると思います。
それで代表の安田が本を読んだ結果、当時行っていた年間のMBOに対する課題にバッチリ合いそうだと思ったのがきっかけでしたね。
会社全体で取り組んでみたいというのがあって2018年に導入を開始したのですが、その時はさほど上手くいってない印象でした。
チェックインもウィンセッションも無く、個人の目標管理を「OKR」という言葉でやっていました。
変化のきっかけとしては、2019年にResilyさんに相談をしてツールを一部導入したことですかね。
当時導入初期だったので「OKRとは」とか「導入の仕方」を教えていただいて、そこでようやくOKRがインストールされたと個人的には感じています。
Resilyの西川さんに勉強会を行っていただいて、それまでにOKRをやっていたのに「へー!」ということがたくさんありました。今までやっていたのはOKRではなかったんだな…と。
Resily:
2019、2020年と導入を検討する中で、Resilyを選んだのはどういう点で自社にフィットすると考えたのですか?
荒井:
2019年時点では、他のOKRツールが機能していなかったから、という点ですね。手触りが悪かったり、バグってたり、アクセス権の管理なかったりとか、そもそも要件を満たしていなかったんです。
2020年の観点から言うとOKRツリーのところですね。OKRツリーで可視化ができて、全員がそのプラットフォームで一緒に活動できるかというのが1番重要なところでした。
OKRを寸劇でトレーニング。遊び心のあるOKR浸透への取り組み
Resily:
ウィンセッションに寸劇を取り入れたとお伺いしたのですが。
荒井:
そうですね、チェックインとウィンセッションを全社展開するにあたってのトレーニングを寸劇形式で行いました。寸劇にした理由としては、講義形式でチェックインとウィンセッションは教えられないという判断があったからです。
チェックインとウィンセッションを自分で作れるようになれば、現場に戻ってもすぐにやれる状態になっているので、自分で作るならそれを演じようということで寸劇になったという感じですね。
Resily:
テーマパークのキャストとしての寸劇だったんですよね?
荒井:
架空のテーマパークのキャストを演じてもらうという寸劇を用意しました(笑) 事前にテーマパークとOKRの設定は用意しておいて、その状況で「どういうチェックインをしますか?」、「どんなウィンセッションをしますか?」というのがお題でしたね。
ウィンセッションって、スタンスひとつで場を良くすることも悪くすることもすごく簡単なんです。なのでワークショップを開き、最低のウィンセッションと最高のウィンセッションを演じてもらうというワークを行いました。そうすることでアンチパターンとベストプラクティスを自分たちの中で腹落ちしてもらうことができましたね。
Resily:
ちなみに最低のウィンセッションってどんなものでしたか?

荒井:
例えば「〇〇くん、今週はどうだったんだ」という質問から始まって、「今週は〇〇を3件できました」「なんで3件しかできなかったんだ!」みたいな追求になっていくという感じで、最終的には演技ですけど泣いて出ていっちゃう人がいたりとか…(笑)誰かがどこかで経験した事があるような報告会のような場面ですね。
ワーク自体はすごく楽しくて、だいたい最悪のウィンセッションの寸劇は大爆笑です。
雰囲気を良くしようというところに全振りしているので、自分だけじゃなく周りのメンバーも盛り上げるのを協力してくれます。そうすると自然と「いかに盛り上がるか」のチーム対抗戦みたいになってるところがあり、「ここのチームは結束強いぞ」というのを見せつけ合う感じになってますね(笑)
OKRの基本は押さえつつも、決まった型は作らない
Resily:
全社ウィンセッションについて具体的に大きかった手応えは?
荒井:
初回なので、各チームがどんなOKRを設定しているのかや、どういう取り組み状況なのかを共有したくてやったんですが、アンケート結果をみる限りほとんどの方が10点満点で7点以上つけていたので、まあまあ良かったのかなと。
会社として感じられた手応えは、全社ウィンセッションに参加している人数がかなりのものだったので、会社全体としてOKR導入を肯定している状況が作れたということですね。
一部のユーザー、メンバーが勝手にやっている事というよりは、きちんと会社全体の活動としてやることになったっていうのを見せられたのは良かったです。
Resily:
OKRを実際に運用してきた中で、特に効果を感じられたものはなんでしたか?
荒井:
個人の自立を促す効果はすごく感じています。理由としては、ObjectiveとKey Resultsの設定から、レビュー、チェックイン、ウィンセッションまで全て自分で管理するので、完全に自立した状態になるからです。
そうするとメンバーから出てくる改善とか取り組みに対するアイデアは、そのチームのリーダーでは出ないような事まで飛び出したりするので、個人の持っている能力が発揮されるようになっていると感じます。
それに加えて、一体感も強化されているなとアンケート結果からも感じますね。よりOKRという単位の一体感は週次のコミュニケーションによって強化されていると思います。
Resily:
OKRに取り組んでいる人自身がモチベーションが上がる工夫などはされていますか?
荒井:
本気のKey Resultsと空元気を出すためのKey Resultsの2つを設定したりしてます。本当にマイルストーンになってるKRと毎週伸びるKRがあるので面白いですね。こうした部分の遊び心が全社に共有できているというのが上手く行っている理由の1つでもありますね。
あと、OKRを運用し始めて1番に感じたことなんですが、全社で決まった型は絶対に作らない方が良いということです。上手くいっているチームの特徴として、自分たちで振り返りを毎回して、自分たちのやり方を作ろうと努力しているところが1番上手く駆動していますね。
大きな会社にとってそれは難しいかもしれないんですけど、自立型のチームを作る練習にもなるので、型は決めずにチームに判断の命を残していった方がが良いっていうのはあります。
Resily:
いろいろ本に書いてあるOKRの作法はあると思いますが、押さえるところは押さえつつ遊び心を出して運用するというのはとても良いですね。

(参考:クリエーションラインの全社ウィンセッションについてはこちらの記事もご覧になれます
https://www.creationline.com/blog/tadahiro-yasuda/35081 )
OKRの難所はマネジメントにあり
Resily:
逆に、感じている課題はありますか?
荒井:
メンバーの意識の変化を促すことができて、会社の中でも大きなムーブメントを起こせている状況なんですけど、そのマネジメントが今ブロッカーになっている状況を迎えているので、次の課題はそこかなと。
OKRは自立を評価するようなフレームワークだと思うので、コマンドアンドコントロールのマネジメントを得意としているような人のやり方はあんまり相性が良くないと思うんですね。サーバントリーダーシップや自立を促すマネジメントをしているところにはきっと相性が良いんだろうなという感じはします。そのマネジメントのスタンスの切り替えが求められる点は難易度が高いと感じました。
特に会社の歴史が長ければ長いほどマネジメント手法は組織単位で染み付いていると思うので、特にこれから取り組もうとしている大企業にとってはかなり敷居の高い課題なりうるかなと。こうしたものは研修で変えられるような性質でもないですしね。
クリエーションラインは比較的小さな会社でカルチャーとしても若いので変化しやすい部分があるんですけど、それでも課題は感じるので、企業が大きくなればなるほどそこは難しい部分あるだろうなとは感じました。
そこのマネジメントの切り替えに関しては自分の中でまだ答えが出てない課題ですね。
Resily:
最後に、荒井さんからこれだけは伝えておきたい事があれば是非伺えればと思います。
荒井:
これから導入する企業も多くなっていって、結構大きな会社でもこういう取り組みをしようっていうのが出てくると思うんですけど、計画しすぎずに導入してもらうのがいいんじゃないかなってのが、伝えたいことの一つではありますね。
実験してそこからの学びを得てやり方のアプローチをどんどん変えていくような形での導入が理想かなと思っています。やっぱり担当者だときっと全部を決めて、チェックインとウィンセッションの手順書みたいなものを作ってデリバリーしたくなっちゃうと思うんですけど、それはやらずに。小さく始めて実験を繰り返すっていうので導入を進めるのがいいんじゃないかなと思ってます。
OKRを浸透させるには社員の協力が不可欠
これまでクリエーションラインのOKR導入の背景、導入効果、課題感、実践の工夫などを聞いてきました。
一番の特徴は「OKRの基本は押さえつつも自社のオリジナルを取り入れる」という点です。OKRの型を忠実に再現しようと試みても、自社の状況や従業員の状態に合わなければ逆の効果を生んでしまします。
まずは、基本を押さえ、自社にフィットする形はなにか?というのを考えて実行することが大切と言えるでしょう。
そして、導入の成果を見るためには社員ひとりひとりの協力が不可欠です。クリエーションラインのように楽しみながら全社を巻き込んでいけるOKRを取り組んでいきましょう。
他の導入事例
